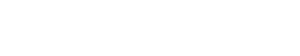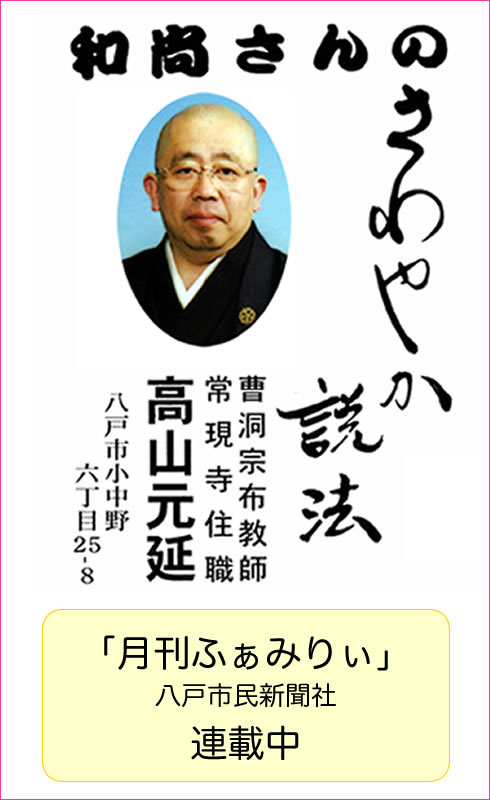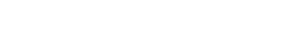和尚さんのさわやか説法322
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
今月号の「さわやか説法」は、「十牛図」の第4図「得牛」である。
今までの第1図の「尋牛」は、自己本来の心を牛に例えて、探し尋ね、第2図の「見跡」は、その牛の足跡を見つけるものであり、そして第3図「見牛」に至ってやっと牛を発見するのであった。
そして第4図では、その見つけた牛を捕らえる「得牛」だ。
-では-
「得牛」とは、如何なることを説かんとしているのだろうか?
この第4図「得牛」では、牛の姿の全身が描かれている。
第1図では、尋ねるだけであるからにして探し廻る牧童だけであり、第2図では、牛の足跡だ。
そして、第3図は、牛の尻尾(しっぽ)のみが描かれているのであった。
-さあ-
探し廻って、今日まで出逢うことのなかった「牛」の全身に出くわした。
「どうして 捕まえようか?!!」
「逃がしては ならぬ」
この第4図「得牛」の「頌」には、こう説かれている。
竭尽神通 獲得渠
心強力壮 卒難除
有時纔到 高原上
又入煙雲 深処居
漢文は実に難しい。では、和訳してみると神通(じんつう)を竭尽(けつじん)して、渠(かれ)を獲得(かくとく)す
心、強(つよ)く、力、壮(さか)んにして 卒(にわ)かに除(のぞ)き難(がた)し 有る時は、纔(わず)かに高原(こうげん)の上(ほと)りに到(いた)り
又(また)、煙雲(えんうん)の深処(じんしょ)に入(い)りて居(きょ)す
と読むが、まだまだ難しい。
そこで、更に意訳して、分かりやすく解説するならば
やっと 探し求めていた「牛の姿」に出会った。
牧童は一生懸命がんばって とうとう牛を捕まえ 獲得することができた。
しかし、牛の力は強くて 暴れ回り、そう簡単には手に負えない。
突然、高原に駆けのぼったり、また遠き山の煙たなびく雲のかなたに居すわってしまう。
このように 牛を見つけ獲得しても 思うようにならないものだ。
意訳すると、このような内容だが、果たして?、どのような教えを説こうとしているのであろうか?
これは「自己の心」のあり様を説いているのだ。
人間の心は、それぞれ異るし、思いも違う。
ある意味で、心というものは、その人なりの「自己中(じこちゅう)」でもあるからだ。
それは、頑(かたく)なであり力も強い。
それは荒々しい牛が暴れているようなもので、なかなか除くことが難しい。
「自己の心」とは、ある時は、高原の頂きに上り、目の前が広くパッと明るくなったような心境になったり、
あるいは、煙雲のかなたに包まれ、深い処に居すわってしまうかのような心境になる時もある。
まことに、牛は、どこに居すわるか、とめどがない。
それと同じ様に「自己の心」というものはとめどがないものだ。
こういう意味ではなかろうか。
古代中国、6世紀前半、南北朝時代のことである。
梁(りょう)の国に、「武帝」という皇帝がおられた。
在位は502年~549年であり、その間、仏教保護と文化興隆に意を尽くし、多くの伽藍造塔を建立しては、国を統率繁栄せんと願った。
当時の栄華を物語る漢詩に「江南の春」がある。
千里鳴鶯 緑映紅
水村山郭 酒旗風
南朝四百 八十寺
多少楼台 煙雨中
これは、唐の詩人、杜牧の有名な漢詩であり、梁の武帝の時代からは300年後の9世紀の作である。
千里四方 広々とした ここ江南(現、南京)の地は あちこちで鶯が鳴き 緑の山々からは いろいろな花が咲き まさに のどかな春の真只中にある
水辺の村々や 山合いの村々には 多くの人々が行き交い 酒屋旅籠の旗が春風に揺らいでいる情景が見える
思えば かつて南朝の頃は 仏教が盛んで480もの寺院が建立されてたという
今もなお その多くの楼台が名残りをとどめ 春雨の中に煙って見える
との過去の栄華と、今の春真只中の情景とを煙雨として表わした詩である。
ここに梁の武帝が多くの寺院を建立して仏教保護と自己の帰依信心に尽くしたことがうかがい知ることができる。
その武帝のもとに、はるばる印度の国から、中国に渡ってきた僧がいた。
その僧こそ、中国に「禅」を伝来された達磨大師であった。
武帝は達磨大師を招き入れ、「私は、こうして仏教興隆に努め、多くの寺院建立をしてきたが、如何なる功徳有りや?」と誇らしげに問うた。
-そうしたら-
達磨大師は、何と答えたかというと
「無功徳(むくどく)」と言ったのである。
これには、武帝は驚いた。内心、「自分の功徳を称賛してれるもの」と期待したが、
「功徳なし!!」と達磨大師は喝破したのだ。
そこで、武帝は、
「では、無功徳とするならば、仏教の真理たる最も大切な第一義とは一体、何でしょうか」
「聖諦第一義(しょうたいだいいちぎ)とは?」と問い返した。
すると、またもや、
「廓然無聖(かくねんむしょう)」と突き放した。
つまり、「聖諦は如何るものや」に対して、「無聖(むしょう)だ!!」と云うのだ。
武帝は、ますます困惑してしまった。
「それなら、仏教の聖諦を伝来する為に、この中国、梁へ渡来してきた、私の目の前にいる貴僧(あなた)は、一体、誰なんですか?」
「朕(ちん)に対する者(もの)は誰(だれ)ぞ?」と聞いた。
すると、達磨大師は間髪を入れず、こう答えた。
「不識(ふしき)」(知らん)
この武帝と達磨の問答において、達磨大師は、武帝に何を教え説かんとしたのであろうか。
-それは-
「武帝の心」を戒め諭(さと)しているのである。
武帝に対する達磨大師の3つの共通する
「無功徳」
「無聖」
「不識」
との答えは、3者とも「無」「不」の否定語である。
この「無」は「有る無し」との「相対の心」を喝破したものであった。
-つまり-
分かりやすく例えるならば、「無心」なる自己の心なのだ。
「無心」を、皆さんはどう読むであろうか?
「無なる心」と読み、決して「心が無い」とは読まないであろう。
さすれば、「無功徳」は「無なる功徳」であり、「無聖」は「無なる聖諦」であり、かつ「不識」は「不なる識」とのことであった。
即ち、単なる否定の「無・不」ではなく、「功徳」も「聖諦」も、そして「識」においてもその真実の姿、本来のあり方そのものをズバリと示したのだ。
武帝の「有るとか無い」とかの執着する除き難い心を喝破したことにほかならない。
-ひるがえって-
『十牛図』の「得牛」で説くところの「自己本来の心」とは、この「無」という「絶対無」を説かんとしている。
「有無相対の心」はまさに、あっちこっちと揺れ動く暴れ牛のようなものだ。
「得牛」の「頌」にある「心強く、力、壮んにして、卒かに除き難し」だ。
故に「無なる心」において、はじめて、その心に気づくことによって、それを除いて「得牛」するのである。
「自己中」なる執着の心を除き放った時こそ「自己本来の心」を得ることになる。これこそ、この第4図「得牛」の教えではないかと、私は愚考愚説する。
合掌