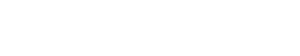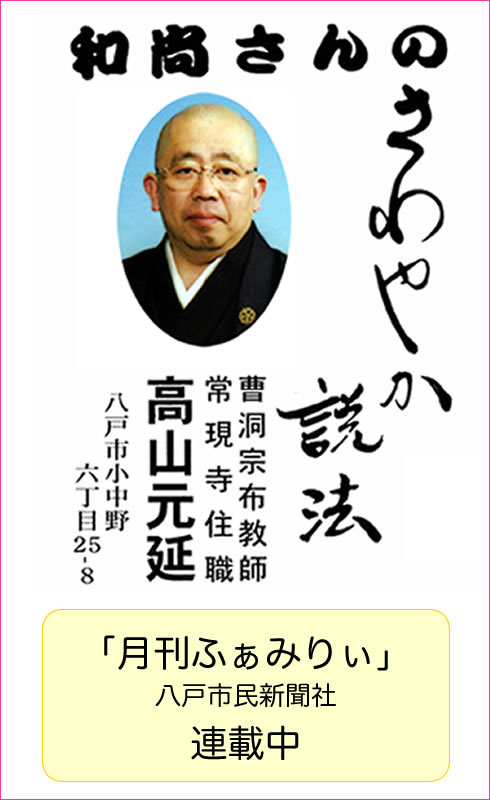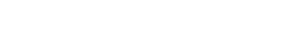和尚さんのさわやか説法160
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
今月号の「さわやか説法」は、ある病院のベットの上で書いている。
実は、ここに至るまでには三日間の私にとっての「痛みと苦悶」のドラマがあったのだ。
今から思えば、それは先週の金曜日の午後1時頃から始まった。
11時からのお葬式を終えて「茶の間」に帰ってきた時、左脚の膝カブのあたりに痒(かゆ)みを覚えた。そこには、ちょっとした皮膚炎がある。膝の皮膚炎は亡き父親和尚にもあり、正座がつきものの一種の職業病なのか、それとも師子相伝なのか、いつものように薬を塗りながら、その痒みに耐えきれず、掻(か)いたというより、かっちゃいてしまったのだ。
この些細な「かっちゃき事件」が、あとでとんでもない事態に発展するとは、その時は予想だにもしえないことであった。
—時刻は進む—
私は、その日、青森出張の為、小中野駅発14時32分発の八戸線に乗るべき着替えをしていた。
その時、身体にブルッと寒気がしたが、暖房も入っていない部屋のことであるから、これもまたいつものことであると思って着替えを済ませた。
台所にいる奥様に留守のことを頼み、外へ出ると寒さがとてつもなくこたえ、歯がガチガチと鳴った。
「あら、大丈夫?何か変よ」という言葉に、
「なあーも たいしたことないよ」と、さえぎって歩き出した。
小中野駅は高架線上の駅である。ことのほか風が強い。そこで寒さに震えながら列車を待っていると、猛烈に腰が痛くなってきた。
やってきた列車に乗り込み座席に腰を伸ばすかのようにして座ると、幾分やわらいだが身体が小刻(こきざ)みにプルプルと震え始め、それが止まらないのであった。
やがて八戸駅に到着し、15時05分発「つがる13号」に乗車した。
—そしたらである—
今度は、腰の痛みと共に下腹部の膀胱(ぼうこう)付近が突如(とつじょ)として痛み出し、お便所にいきたくなった。便所では、うなり声を出しながら、オシッコをした。出す時も出し終わってからも急激な痛みが襲うのであった。
それがまた、5、6分間隔で尿意をもよおすものだから、痛みは止まず、腰と下腹部に手を当てながら、悪寒(おかん)にも耐えるという「三重苦」の体調であった。
「どうして、こんなに痛くて寒気がするのだろう。風邪やろか」
「奥様のいうとおりにして出張中止にすればよかったかも」 と後悔はしたが、後の祭りであった。
「そうか、三沢で降りて、またもどって病院に行こう」
と思った瞬間、車内放送がピンポーンと鳴った。
「御乗車の皆様に御案内申し上げます。」
「弘前行き『つがる13号』の到着駅は、青森、浪岡、終着弘前です。」
「なお三沢、野辺地、浅虫駅は止まりません」
この放送を聞いたとたん、悪寒と痛みは更に倍加した感じがし、
「青森までかあー」 と思わずため息がもれた。
青森到着まで、こんなに時間を長く感じたことはなかった。
オシッコもこんなにも行ったことはなかった。
何回も、それもチョッピリずつ、まさに頻尿と貧尿のくり返しである。
駅に着き、会議のあるホテルに向い、フロントで体温計を借りて計ると、39度2分あった。こりゃ会議どころじゃないと判断し、その旨を知らせるべき会議室に行くと、皆なは私の変調が一目で解ったらしい。
「早く病院に行け」との激励やらアキレ声に追い返されて、またフロントで体温計を借りながら近くの病院に行く手配を頼んだ。今度は39度8分に上昇していた。エレベーターのせいであろう。
病院では、私の様子を見てとって、すぐ対応してくれた。熱は40度1分になっていた。
青森の看護師さん達は、面倒見がいいのか、やかましいのか、暇なのか、次から次へと病気のことばかりでなく、なんやかんやと速射砲的に聞いてくる。
こちとらは痛みと寒さに苦しいものだから咄嗟(とっさ)には答えられないがそれでも冗談をかましながら応戦すると、
「まあ、この患者さんたら、40度もあるのにおもしろい人。」といって、
またぞろ集団で聞いてくる。
津軽弁で 「かちゃましねェー」 と叫びたかったが出来なかった。
それは一生懸命、私を励まし、看護してくれる心が解るからであった。
先生が来られ問診し、今までの症状を聞くと、ニッコリ笑って
「これね尿管結石、石がポロッと排泄されるとすぐ治るよ」と言った。
でもオシッコを採ったデータを見ると、
「ちがうなぁ」 「じゃ、横になって」
と言うと、私の下腹部を撫でたり、もんだり色々と手でさすって診療し始めた。
—そしたらである—
強烈に痛かった下腹部が徐々にやわらいできたのであった。
看病、看護の「看(かん)」の字は「手へん」に「目」である。
即ち、手という目で病を「看(み)」るのである。そのことが「医者の手」によって病を看る、病をやわらげることになったのだと、私は思った。
「先生、痛みがなくなってきました。」 すると
「今はやりのインフルエンザかな」といって、先生自ら検査棒を鼻の穴に突っ込んだ。
「じゃあね、検査の結果が出るまで、処置室のベットで横になってて」
「予防接種した?してないでしょ」
「多分、インフルエンザだから点滴すれば、楽になって八戸に帰れるよ」と肩を叩いた。
処置室へ行くと、またぞろ、あの看護師さん達がやって来て、私が和尚だと解ったことで興味津々、お寺や仏事のことをアレコレ聞いてはおもしろがる。
「まんずまんず、津軽の看護師さんは…」 私は感心してしまった。
結果が出たという。
「陽性反応ではなかったから点滴はしないけど応急的な注射をするから、後は八戸の病院にいってしっかり治すんだよ」と、チューブをした左腕の静脈をパシパシと叩いて注射した。
その激励の言葉と仕草に私は思わずクスッと笑ってしまった。
私は、青森での発病を通して「津軽の人」の気質というか、「津軽の看護師さん」の気質を少し見たような気がしたのであった。
17時43分発の青森発の列車に乗り、満身創痍(まんしんそうい)的に帰宅した。
次の日、朝一番で相も変わらなかった高熱と痛みと尿意を伴って八戸の病院を訪問した。
そこでは私は、南部の気質、「南部の看護師さん」の気質をこれまた見させてもらった。
このことは次号に「さわやか説法」することとして、今回と次号とで私は何を説きたいのか、それは三日間で津軽、南部の個人病院を経て最終的に地域医療の中核である大病院で病を看る方々の気質と、その献身的な対応を通して感じた「看病、看護」というものの本質を仏教的に私なりに考えてみたいからであった。
では、「南部の看護師さん気質編」は次号のお楽しみにして。
合掌