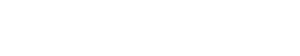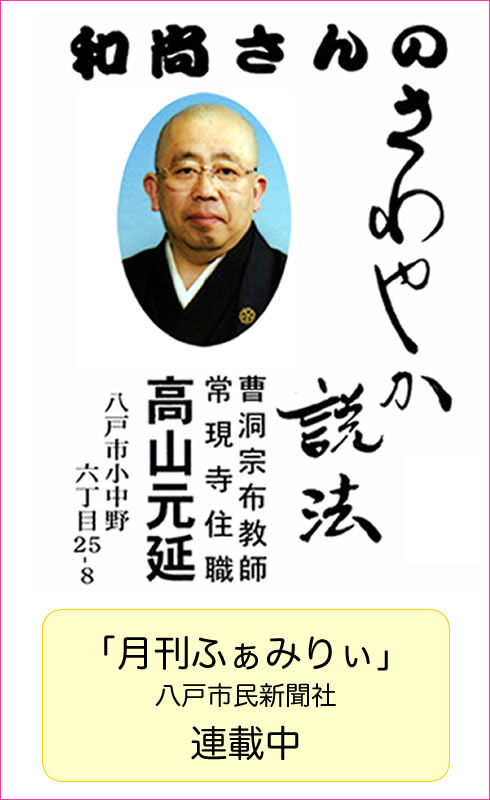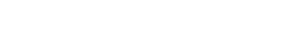和尚さんのさわやか説法162
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
先月号までの「さわやか説法」で、私の闘病体験を通して「津軽」と「南部」の看護師さん達の気質から「看病、看護」のことを考えてみた。
では、今月号で、私は何を読者の皆様にお話したいのか?
—それは—
「看病」ということの意味と、その本質を、昭和61年に亡くなった父親、高山不言大和尚様の「最後の言葉」から説法してみたい。
時は、今から逆上ること十九年前、昭和60年9月の頃だった。
父が、胸のあたりを押さえ、
「何だか、この辺がモヤモヤする」
「きっと回虫がいるにちがいない」と、言っては胃薬を飲んでいた。
皆様は「回虫」ってお解りでしょうか。
若い年代の方々は「えっ、どんな虫?」と思われるでしょう。
現代では、もう死語となった言葉ですが、中年以降の方々は覚えておられるでしょう。
回虫とは、昔不衛生だった時代、野菜等の食物からその卵が体内に入り、小腸や大腸で孵化し成長した寄生虫のことである。
私も幼い頃、体験したことがあるが、まあともかく腹のあたり、下腹部がモヤモヤするというか、体の中から痒いのである。
父も、そんな状態だったのであろう。
「病院に行ってみたら」と何回も勧めるのだが
「病院には行かん!!」の一点張りであった。
病院嫌いの父を説得する為、お酒好きの弱点をついて、私はこう切り出した。
「人間ドックにでも入って調べてみたら」
「何でもないと、お医者さんからお墨付きをもらえれば、おいしくお酒が飲めるよ」と、言うと「そうだな」と頷(うなず)いた。
早速、ドックの手続きをすまして一泊二日の検査入院となった。
次の日、父を迎えに病院にいくと、すぐさま結果は本人でなく、息子であるあなたにと言われた。
言われるままに診察室を訪ねると、担当医の先生が、食道造影のレントゲン写真を照明版の上にグィッっと差すと、おもむろにこう言われた。
「ほらっ、ここの部分を見てごらん。」
「上から、まっすぐ降りてきて、ここの部分が盛り上がっているでしょ」
私は、先生の指さす箇所を凝視した。なるほど、白い空洞の部分が喉元(のどもと)より下にさがってきて、そこへくると急に白い部分がせまくなっているのだ。
「あなたのお父さんは食道癌です。」
「それも大分(だいぶ)、悪い」
「すぐ入院するように」
たてつづけざまに言われた私は、急に顔から血の気が引いていくのがわかった。
放射線療法の日々が続いた。病院嫌いの父ではあったが、少しは胸のモヤモヤがとれてきたのであろう。黙って治療を受けていた。
12月を迎えたある日担当医から呼ばれた。
「どうなされます。あとは息子さんであるあなたの判断にまかせます。……」
急に言われた私は、とっさに声を出すことができずにいた。
今回の父の病名は本人には告知はしていない。20年前のあの頃は風潮として本人告知はタブーでもあった。
診察室の時計の音だけがやけに大きく響く。
やっとの思いで私は声を出した。
「ところで、先(せん)、先生(せんせい)。
父は、あとどれくらいもつのでしょうか、どのくらい…。」
「そうですなぁ、早くて年内、遅くても年を越して春くらいですかな」
「じゃ、先生のおっしゃる抗ガン剤療法をすれば、どれくらい長生きするんですか…。」
「まぁ、1、2ヶ月から半年ぐらいかな」その淡々(たんたん)としたもの言いとは逆に、
私は素っ頓狂な声で「たったそれだけですかぁー」と叫んでしまった。
「抗ガン剤は苦しいし副作用もあると聞いてますが、それをやらないで他の治療法は…」
「まぁ、しないのであれば、病院としては何もやることはないということですな」と、
退院を勧められた。
私の覚悟は決った。
「はい、わかりました。では、父を家に連れて帰ります。」
病室にもどると、妻が心配そうにして私を待っていた。
「退院の許可がおりたよ」 と、精一杯の笑顔を作って父に話すと、
「やっと帰れるな。これで正月は寺で迎え、餅も食えるな」
「よかったわねェ、方丈さん。ワタシ、たくさんの御馳走を作りますよぉ」と、
妻は帰り仕度を手伝い始めた。
—しかし—
私達も、家で待っている母も誰もが知っていた。もう餅は、食べたくとも食べれないことを…。
それからが大変であった。私や母というよりも、嫁である妻が献身的に看病、身の回りの世話に忙殺されていった。檀家さんでもある小中野町の山道先生による毎日の往診に頼りながら、日々の闘いというより病との共存であった。
年内と言われたのが正月を迎え、2月には早めの「喜寿」の御祝いをやり、不思議と平穏な日々が過ぎていった。
3月に入って、とある日、いつものように晩ご飯を枕辺に持っていった。それはおチョコ一杯のお酒と蜂蜜湯そしてアイスクリームが少しというものである。
ところが、その日はほんの一口をつけると「もう下げてよろしい」という。もう少しと進めても、ただ首を横に振るばかりで、こう静かに一言一言区切りながらこう言われた。
「看病は、慈悲の、徳を、養う、最大の、修行なり……」
「看病は、慈悲の、徳を、養う、最大の、修行なり」
その夜、私は自室でこの言葉をくり返す度に涙があふれでた。
「もう長くはない…」
そして父は何を俺に言いたかったのか。
「今まで看病してくれてありがとうよ」と言いたかったのか。
「それは、ちがう」
と自答する。それとも「お前も少しは看病が出来るようになったな」とほめてくれたのか。
「それもちがう」
きっと、こう言いたかったのではないか、
「ワシが亡きあと、住職としての寺を譲るということは、人を看病するように、慈悲の徳がなければいかん。慈悲の修行をせよ」という重い鉄槌であったのだ。
事実、この言葉が「最後の言葉」となった。
「慈悲」の心とは、「与楽抜苦」つまり、人々を慈しみ、心の楽しみ、安らぎを与える心であり、人々の苦しみを抜き、相手の悲しみを共にする心をいうものである。
読者の皆様の中で、病院や家庭で看病看護している方々へ、
「あなたの看病は、あなた自身の慈悲の徳を育てていることですよ」
「だから疲れているでしょうが、がんばって下さい」と私は言いたい。
また、私達の日々の行いや仕事で人々に対することは、「看病」をするような心で取り組まなければならない、ということでもある。
だからこそ、こうしてあらためて考えてみると、方丈様の「最後の言葉」は私でなく看病してくれた奥様に言いたかった御礼の言葉ではなかろうか。
合掌