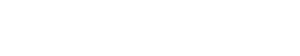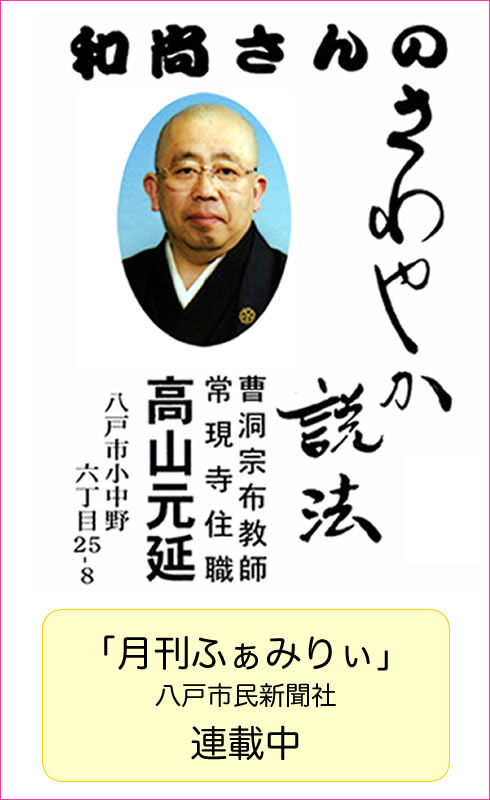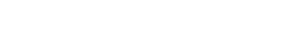和尚さんのさわやか説法171
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
今月五日、子どもの日に当常現寺を会場に「篠笛(しのぶえ) 語り部(かたりべ) 小中野幻夜(こなかのげんや)」(主催 小中野生(い)き活(い)き市場)というイベントが開かれた。
当日は、本堂の御本尊様の前に舞台が設置され、ローソクの灯の中、幻想的な笛の音と民話の語りが響き渡った。
笛の音が静寂の中にさらに静寂をかもし出し、語り部の声が聴き手の私達の心と一体となって、いやがおうでも民話の世界に没入(ぼつにゅう)していくのだった。
—誰もが、うなった—
そのシチュエーションの中に、実は、この私、高山和尚も出演し、語り部となったのだ。
私が冗談で「僕は笛は吹けないけど、ホラなら吹けるよ」と篠笛奏者の小野さゆりさんに言ったとたん、一番最後の場面で是非とも話をしてくれということになった。それも篠笛でバック演奏もつけてあげるから「和尚さんと私のジョイント民話語りだね」とトントン拍子に物事は勝手に進んでしまった。
こうなったらと腹が決まると、私は部屋にこもると約30分で創作民話五分間バージョンを書き上げた。
—実は—
—いともたやすく書ける理由があったのだ—
前号で一番末尾に書いた「ここ掘れワンワン」「ここ掘れ ワンカップ、ここ掘れ ワンカップ」の花咲か爺さん改め「花酒(はなさけ)爺さん」のダジャレを飛ばしたことの題材があったからこそ書き上げれたのだ。
—その民話は、こうして始まる—
むかーし 昔。南部は小中野の村に善良なる和尚さんがおったそうな。その和尚さんは村人から「花酒(はなさけ)爺さん」と親しみをこめて呼ばれていた……。
と、まあ。私が身振り手振り、その上、笛が調子をつけてくれるものだから。しんみり聞かせる創作民話のはずが、大爆笑、抱腹絶倒の演芸場になってしまった。
—トッホッホ(涙)—
—とんでもないことになってしまいました—
—さて—
話を本題にもどそう。
前号で、お爺さん夫婦が「しろの臼(うす)」で餅をつくと、それが黄金色の小判となり、それを見ていた、となりの欲張り爺さんが、無理やり、その臼を借りて、ペッタン ペッタン 餅をついたが、一向に黄金色に光(ひか)らない。
—そこで—
その餅は、どうなったのか。欲張り爺さん夫婦は、小判をつき上げることに成功したのかどうか。
で、前号は終了した。
「じいさん。ちい〜とも餅の色が変らんなぁ」
「そうじゃ!!丸くすればいいかも」
二人は、餅を小さくちぎり丸め始めた。
—すると—
白い餅は、黒いすみになって、バチンバチンとはねて、二人の顔をまっ黒にしてしまった。怒り心頭の二人はなんと、臼を叩き割ってしまい、かまどで燃やしてしまったのだ。
しろの臼を燃やされてしまった優しいお爺さんは、それはそれは悲しんだ。
そこで、そのかまどの前にたたずみ、燃やされた灰をすくいあげ、思わすつぶやいた。
「しろ……」
しろの形見に、せめてこの灰を持ち帰ろうと、お爺さんはかごに入れ、「この灰を畑にまいて しろの供養としましょう」
おばあさんがそう言うので、お爺さんは畑にまきにいった。
「しろやぁー」と、灰をまくと、それは風に吹かれて散っていったかと思うと、
—なんと—
枯れた木が光り出しさくらの花が咲き始めたのだ。
「こりゃぁー。不思議なことがあるもんじゃ」
「ばあさん見ろや。サクラじゃ」
「桜の花が満開じゃぁ」
このウワサは、たちどころに村中に広がった。そして、お城のお殿様の耳にも伝わった。
早速、お殿さまはお爺さんのところへやってきた。
「くるしゅうない。さぁ!!桜を咲かせてくれ」
お爺さんは、枯木の上で灰をまき始めた。
「枯木に花を咲かせましょう。」と叫びながらまくと、もう、それはそれは見事な満開の桜と変っていった。
お殿さまは、手を打って大喜び、「これはスゴイ!!日本一の花咲か爺よ」
「ほうびをとらせる」
—すると—
また、あの欲張り爺さんが掛けつけ、「そのごほうび、ちょっとお待ちを!!」
「わたくしめこそ、日本一の花咲か爺であります。この灰で、どっと咲かせてみせましょうぞ」
欲張り爺さんは、かまどに残っていた灰を集めてきたのだった。
そばの枯木の上に登って、勢いよく灰をどっとまいた。
—ところが—
その灰は、そのままお殿さまの頭の上に、バラバラと落ちたのだった。
「ハッ、ハックション」
お殿さまも家来衆も、こりゃたまらんと逃げ出してしまった。
欲張り爺さんは、お殿さまに厳しく怒られ、やっと自分の心に気づいた。
何故、自分が「欲張り爺さん」と村人から言われているのかを。
それからというもの、となりのお爺さん夫婦に謝り、村人達とも仲良くなり、村は「心の花」で満開となったとさ。めでたし めでたし。
これで「花咲か爺さん」のお話はオシマイ。
以上が「花咲か爺さん」の物語であるが、私は前号で、この物語の根底の主人公は、善良なるお爺さんではなく、「しろ」という犬であると書いた。
というのは、その場面場面が変わっていっても、しろが「ここ掘れワンワン」と導いたり、大きな木の臼になったり、最後には灰になって花を咲かせたりで、優しいお爺さん夫婦に幸せを与えようとしていたからである。
そしてまた、この犬の名前が「しろ」でなければならないのか。
—それは—
この花咲か爺さんの物語は、私達に「善良なる」ものを教えたかったにちがいないからである。
その「善良なる心」が「白」という表現なのだ。
—そう、私は思った—
だから、「しろ」以外の名前だったら、この物語は成立しないのである。
「しろ」の心が、最後には、あの意地悪なとなりの爺さん夫婦を改心させ、村中、皆が仲良く幸せになることを語っている。
まさに、枯木に花を咲かせるように「心の花」を満開にさせようとしているのだ。
ここまで前号から「花咲か爺さん」二部作を書いてみて、私自身の心はどうかと問いなおすなら「白」とは言いがたいと思うし、かといって「黒」ではない。
たぶん「灰」色だろう。だから本日は、これにておしまい。
「灰(はい)。さようなら」ってね。
合掌
※参照
日本昔ばなし101 講談社発行