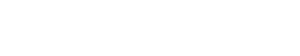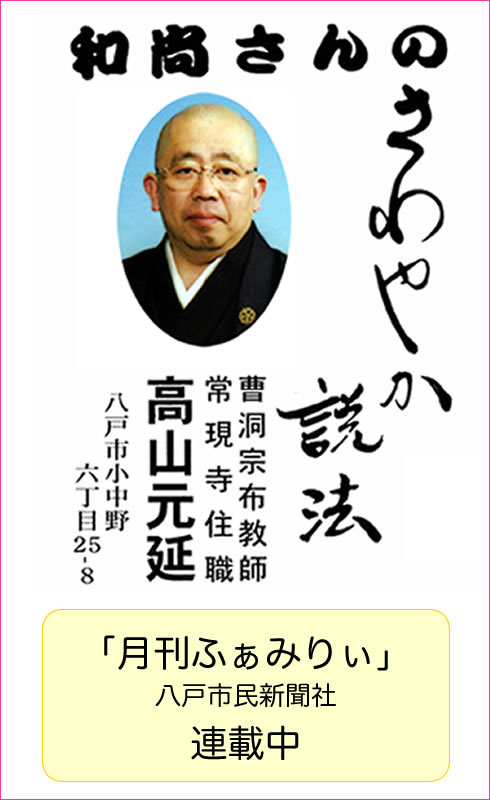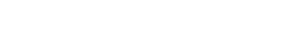和尚さんのさわやか説法323
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
今月の「さわやか説法」は、またまた『十牛図』であり、今回は第5図「牧牛」である。
毎号で語ってきた『十牛図』における「牛」とは、「自己本来の心」を例えている。
この牛を尋ね、跡を見つけ、やっとその牛を発見し、捕まえることが出来た。
でも、その牛は勝手気ままにあちこち動き回る。それでも何とか捕えた。
それが第4図までの物語だった。
第5図では「牧牛」といって、その捕まえた牛を如何に飼いならすかである。
では、この「飼いならす」とは、一体どういう意味なのであろうか。
この牛とは、先程も述べたが、「自己本来の心」である。
この「本来の心」を本当に知る。あるいは自分の知らない「真実の心」に気づき、同化し、そしてその本来の心のままの自分となる。
牛と牧童が一体となって、共に歩む。
いや、むしろ牛の方が牧童に従い歩みよってくる。
それが飼いならすという意味なのだ。
その象徴が、実はこの第5図の「牛」の描き方にあるのではないかと私は思った。
それは第1図、第2図は、まだ牛は描かれていなく第3図、第4図で、その尻っ尾や全身が現われる。
その牛の姿は「黒く」描かれていた。
ところが、第5図は「白く」描かれているのだ。
-つまり-
白は「本来の真実の心」を表現しているのではないか。そう思ったのである。
この牧牛図の「序」にはこう説かれている。
牧牛
前思纔起 後念相隨
由覚故以 成真
在迷故而 為妄
不由境有 惟自心生
鼻索牢牽 不容擬議
またまた漢文だ。
まっこと難しい。
まず和訳してみよう。
牛を牧(か)う
前思(ぜんし)わずかに起(お)これば、後念(こうねん)あい隨(したが)う。
覚(さと)りに由(よ)るがゆえに真(しん)と成り、迷(まよ)いに在るがゆえに、妄(もう)となす。
境に由って、有(う)なるにあらず、これ心(こころ)より生ず。
鼻索(びさく)、つよく引いて擬議(ぎぎ)を、容(い)れざれ。
まだまだ難しい。
そこで、今度は意訳だ。
何かの意識や思いが起こると、たちまち次の意識や考えが浮かぶ。
本心に目覚めることによって、真実と成るが、迷いの心があることによって、妄想と為すのである。
それは境遇や対象のせいでそうなるのではなく、とどまるところ自分の心から生ずるものである。
だからこそ、本来の心である「牛」の手綱をしっかりと引いて、ためらってはいけない。
-つまり-
私達の心というものは、次から次へと思いが浮かんできては迷う。
しかし、自己本来の心に気づけば、真実の心となる。迷いは境遇や相手のせいにするのではなく、それは自分自身の心から生じている。
故に、しっかりと自己本来の心を引かねばならないのだ。
言うなれば、自己本来の心を、しっかりと見つめ、気づき、その心そのものになるとの教えであった。
7月末、全国教誨師連盟の職務で「京都」に行ってきた。
コロナ禍であり、移動自粛で行きたくなかったが、事務局からは懇願され、マスク・手袋に帽子と、ともかく感染防御に徹すべく、意を決して向かった。
場所は京都、西本願寺「聞法会館」だ。
言わずとも知れる西本願寺は「浄土真宗本願寺派」の大本山である。
しかしながら、曹洞宗の私にとっては、初めて訪れる未知なる聖地だ。
午前11時に、本日の会議を打ち合せ、午後からの本番までは自由時間となった。
私は1人、西本願寺御本堂を参拝することとし、聖地なる境内に足を踏み入れた。
その日の京都は、猛暑36℃だ。
玉砂利は乾き切って踏むたびに音がきしみ小石の熱と熱波が襲い掛かってくる。
その上、夏蝉の鳴声がやけに高いのだ。
そこには堂々たる威容を誇る「阿弥陀堂(あみだどう)」と「御影堂(ごえいどう)」が鎮座していた。
どちらも国宝の建造物であり、平成6年には「古都京都の文化財」として「世界遺産」にも登録されているという。
「阿弥陀堂」は修復中で入ることが出来なかったが、「御影堂」は許可されていた。
向拝で熱の帯びた靴を脱ぎ、御影堂の中へ一歩踏み込んだ瞬間だった。
ずしんっとした歴史の重圧と外界の暑さとは異なる涼やかな気圧が私の全身を包んだ。
「ほぉー」っと声ならぬ声が思わず出た。
外の暑さも蝉の声も遮断された清涼静寂なる別世界だった。
その御影堂外陣中央に、1人の若き女性が横座わりにして、内陣奥に鎮座せる「阿弥陀如来」様を見つめていた。
441畳敷きの堂内には、この女性1人のみで、誰一人としていない。
-だからだろうか?-
実に気になるのだ。
これが、おばはんだったら別段気にも掛けないのだが、若き女性だからこそ余計に気になるのだ。……。
トホッホッホ💧💧💧
アホな和尚です💧💧💧
私は遠巻きに気づかれないように、左右の内陣脇間の御尊像を拝覧して回り、外廊下や他の箇所を拝観してまた戻ってみると、あの女性は、まだ、そこに座わっていたのだ。
今度は、正座して合掌をし、御本尊阿弥陀如来様を見つめている。
その姿が、妙に御影堂の閑寂なる空気と一体化しているように私には感じとられた。
不思議な状景だった。
何気なく内陣中央上部を見上げると、そこには「見真」と書かれた扁額が掲げられていた。
その「見真」なる書が私の眼に飛び込んできた時、衝撃が胸に走った。
「見真?」
「見真とは?」
「この女性は、阿弥陀様の真の姿を見ているのか?」
「いや、阿弥陀様を仰ぎ見ながら、自己の真実の心を見ようとしているのか?」
と、私は、私の心の中で叫んでいた。
「見真」とは、八戸へ帰ってから調べて分かったことだが、浄土真宗宗祖「親鸞上人」の大師号とのこと。
その出典は『大無量寿経』の「慧眼見真 能度彼岸」(慧眼(えげん)は真(まこと)を見て よく彼岸(ひがん)に度す)とのことであった。
慧眼とは智慧の眼(まなこ)であり、阿弥陀様、あるいは親鸞上人の眼(まなこ)なのだ。
その眼(まなこ)は人々の真の姿、真の心を見て浄土に救わんとすることなのであろうか。
-とするならば-
あの御影堂の女性は阿弥陀様に救われようとして来ていたのか。
いや、もう救われていたのかもしれない。
阿弥陀様の方から手を差し延べていたのだ。
実は「十牛図」「牧牛」における教えは、牛という「本来の心」「真実の心」の方から寄ってきているとのことなのだ。
それは 牧牛図の「頌」の後段にある。
相(あい) 将(ひき)いて 牧得(ぼくとく)すれば純和(じゅんな)せり
羈鎖(きさ) 拘(こう)すること無きも 自(おのずか)ら人を逐(お)う
牧童が牛を引いて よく飼いならして おとなしくなれば 手綱で拘束しなくても 牛の方から牧童についてくる。
というのだ。
-即ち-
この牧牛とは、牛という真実本来の心と自分とが一体となる。いや、むしろ本来の心の方から導いてくれるとの教えであった。
あの西本願寺の本堂で祈りを捧げる女性に対しても、阿弥陀様の方から浄土へ度すべく救い導いていたのではないだろうか。
実は、私自身も、その場で、阿弥陀如来の真の心に導かれていたのかもしれない
合掌