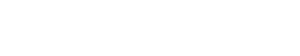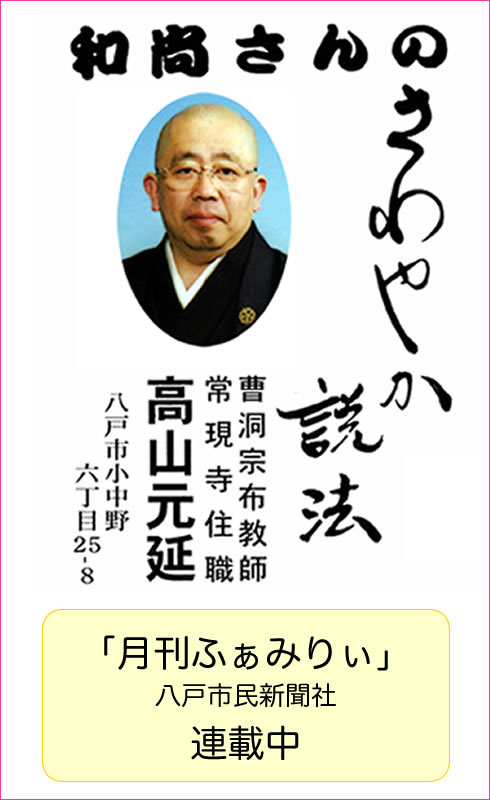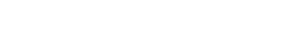和尚さんのさわやか説法262
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
今月号も先月に続いて「鯉する奮闘記」である。
あの「枝川(えだがわ)」という料理屋さんでのアルバイトは、毎日腹を減らしての貧乏苦学生にとっては、「救いの神」であった。
何たって、御飯は腹いっぱい食べさせてもらえるからだ。
板前さんは、お客様への料理は作るが、決して板場で働く自分やアルバイトへの食事は作らなかった。皆なの毎日の食事は「おかみさ ん」が作るのだ。
その「おかみさん」の料理は、店の料理とは違い、まさに「おふくろの味」的な家庭料理であり、これがまた、実に美味しいのである 。
私は、学業はそっちのけで朝から晩まで店で働くようになっていった。
−その時−
起きたのが、先月号で書いた「鯉する奮闘記」事件である。
この事件は、次の日から、常連客の恰好の話題になった。
「へェー。学生アルバイトが、お客さんを怒ったのかぁー」
「酔っぱらった客が、口をパクパクさせている鯉に、酒を飲ませようとしているのを、たしなめたって…」
「ここにいる皿洗いの丁稚小僧が、一喝したってのかぁー」
私は、黙って下を向きながら皿洗いをしていた。
板前さんは、「バカなアルバイトで、申し訳ありません」と低姿勢だ。
カウンターで板前さん相手に盃を傾けていた客達が、こう言った。
「おい!!アルバイト!!」
私は、ギクッとして皿洗いの手が止まった。
「お前!!よくやった」
「さあ!!飲め!!」と、ビールの瓶を突き出した。
「エッ」と小さな声を上げた私は、板前さんの顔を見た。
板前さんは、少し笑いながら、「高山くん せっかくのお客さんからのビールだ。頂戴しなさい」と、洗ったばっかりのコップに目をやった。
私は、怖ず怖ずとカウンター越しに差し出すと、客はなみなみ注ぎ「高山くんっていうのか。」
「出身は、どこだ」
「はい。青森の八戸でっす。」
「どうりで、少し訛っていると思ったよ」
「お前、小っこいわりには、でっかい度胸してるよな!!」
「さあ!!飲め!!」
「いやぁー なんもなんも」
顔を横に振りながらの、八戸訛りが出たとたん、そのお客さんは、
「ワッハッハッ」と大声で笑い「お前!!面白い奴じゃ」と、ビールをあおった。
板前さんも一緒に笑いながら「こいつは、しょうがない奴で…」と、その常連客と語り始めた。
その「鯉の一喝」事件を契機として、板前さんは、私にいろいろなことを教えるようになった。
「枝川」は割烹料理も出すが、本業は「鰻屋」である。
つまり、ウナギの焼き方や魚の焼き方を教えるのであった。関東風のウナギの焼き方は、白焼きをしてから蒸して、それからタレを付 けながら、また焼くのであり、関西風の「直焼き」とは異なる。
このタレが秘伝のタレであり、黒光りした壷が、その長年の風格をかもし出している。
蒸し終った白焼きの鰻を、その壷のタレにドブッと浸して、赤々と燃える炭火の上に置くと、あの独特な「蒲焼きの匂い」が店の中や 、換気扇を通して、道行く人々の鼻をくすぐる。
その火加減、焼き加減を調整するのが、団扇(うちわ)なのだ。
それは竹製の団扇であり、しなやかでありながら、叩くとポンポンといい音がするのであった。
どっかの国務大臣が有権者に配ったようなウチワとは違うのである。(すみません(T_T)ちょっと脱線してしまいました)
この焼くときの団扇の煽ぎ方は、夏の暑い時、自分の顔や体に風を当てるようなものではなくして、柄を右手の親指の付け根部分で挟 み、他の四本の指で、その団扇の背面を叩き、左手の掌で表面を同時に叩きながら煽ぐのである。
その風の調整と団扇の「ポッポポン、ポッポポン、ポッポッポ」とのリズミカルな叩きと煽ぎにより、いやがおうでも口の奥から唾液 が出そうになる独特の香ばしい匂いが生み出されるのだ。
この「焼き方」は、徹底的に仕込まれた。何度も失敗した。焼きが甘いと崩れる。かといって焼きが過ぎると焦げる。蒸し方も同じだ 。
一日、何十枚も焼くし、多い時は百枚以上も焼く、しかしどれ一つとして同じ物はない。一つ一つが微妙に違うのだ。
それを一つ一つ見極めながら、焼いてはタレに付け、付けては、また焼く。
その「焼き」の微妙から絶妙へと変化させた旨さを引き出すのが「焼き方」の役目だ。
−そんな時−
また一つの事件が起きた。
夜の七時。店が一番立て混む時間帯だ。
夕食団欒の家族、会社の飲み友達、サークル仲間の談論風発等々喧騒の最中(さなか)の時のことだった。
板場に奇妙な音鳴りが走った。
おかみさんも板前さんも、そして私も、同時にその音の方向に視線を凝らした。
−何と−
板場にある生ゴミ専用のポリタンクが真っ二つに割れ、中にある野菜や魚類の生ゴミが板場のタタキに散乱したのだ。
一瞬、「ウッ」という唸り声的な息を飲む声が板場を支配した。
しかし、板前さんは包丁さばきの手をゆるめない。おかみさんや手伝いのおばちゃんも、お客さんの料理運びや接客に忙しい。
−その時−
私は咄嗟に、そのタタキに這いつくばり、その散乱した生ゴミを片付け始めた。
私は、この惨状をお客さんに気取らせたくなかった。胸元を濡らしながら生ゴミを全て撤去し、最後に静かに水を流して、何事も無かったかのように元通りの状態にした。
板前さんは、マナ板の前を一歩たりとも動かなかった。
「ああしろ、こうしろ」とも一言も口には出さず、おかみさんも客席から、板場に一歩も入って来なかった。
「終わりました!!」
と、板前さんに声を掛けると、「そうか」との一声。
料理屋「枝川」の中は、平然と、いつもの風景と変わらなかった。
夜、店を閉め暖簾を降ろすと、板前さんがめったに作らない、板さん特製の「まかない料理」を並べ私を待っていた。
「高山くん!!今日は御苦労だった」
「咄嗟なことに、よく何事も無いように、よくやった」
「さあ!!飲め」またビールを突き出した。
「高山くん!!あんたは、いい板前になれるかもしれないな」
「どうだい!!板前になる気はないか」と催促された。
「あんたは、和尚にするにはもったいない。」
「田舎の和尚より、東京の板前のほうがいいぞぉー」と矢継ぎ早やに言うのだ。
私は、とまどいながらも、首を横に振った。
−もし、あの時−
「うん」と返事していたら、どうなっていたのだろうか。
きっと、今の私はなかったにちがいない。
想像するだけでも、心が妙に甘酸っぱさを感じる。
料理をする心構えとして道元禅師は三つの心を説かれている。それが、
「喜心(きしん)・老心(ろうしん)・大心(だいしん)」だ。
喜心とは、字の如く喜びの心であり、作る喜び、食べてもらう喜び、そして美味しいと味わう喜びのことだ。次の老心とは、相手を思いやる慈しみの心であり、「おもてなし」のことである。最後の大心とは、大きな心で、食べてくれる人のことを思う寛(ひろ)い心をいうのであった。
つまり、料理を「つくる喜び」「おもてなしの喜び」そして「美味しさの喜び」。
これが「三心」なのだ。
まさに、これは料理屋「枝川」の「心」であり、板前さんから教えずとも教えられていた「心」であった。
私は、板前修業を通して、やっぱり、禅の修行をし仏教を学んでいたことは間違いない。
合掌