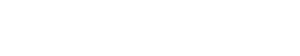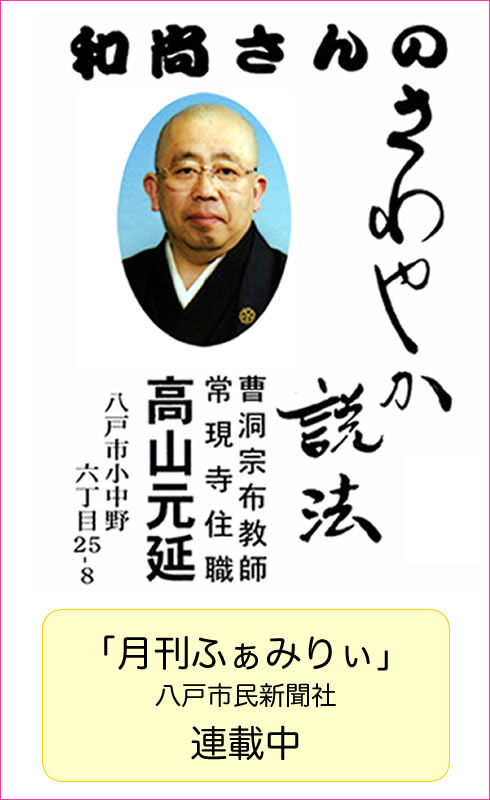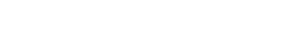和尚さんのさわやか説法260
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
私は、1月、2月の厳寒期になると決ってある「出来事」が思い出される。
それは、高校3年生の時のことだ。
このことがなければ現在の「私(わたくし)」はない。人生転換の出来事であった。
高校3年生の時、親から与えられていた月々の「おこづかい」は千円であった。
時代は昭和40年代初期であり、板垣退助が描かれた百円札十枚の入った封筒を父たる不言和尚から「大事に使うように」とのお言葉をいただきながら、「はぁはぁー」とひれ伏して頂戴していた。
ところが、こちとらは、もらえばもらったでしめたもの。十枚の百円札は羽が生えたかのように、またたく間に小さな財布からは飛び去ってしまう。
親の「大事に使うように」との苦言も、もらった時だけのことでそれも一緒にぶっ飛んでしまっていた。
月の半分も過ぎると飛び去ったあとの鳥の足跡すらも残っていない。すっからかんとなっている状況が何ヶ月も続いていた。
1月末のことである。意を決して、父親方丈の前に正座して、こう言った。
「おとちゃん!!お小遣いを値上げして下さい」
「何とか、お願いできませんか」
私は、きっと親父のカミナリが落ちるだろうと覚悟して、恐る恐る切り出した。
—ところが—
案に相違して「あい分かった。」と素直に応じたものだから私は拍子抜けがしてしまった。
「ところで、いくら値上げしてもらいたいのじゃ」と、問い返されたものだから、心の中では「千円値上げの、二千円!!」と叫びたかったが、拍子抜けのせいか「五百円!!」と言ってしまった。
「そうか、千五百円か!!よかろう。では来月から千五百円にしてやる」
私は喜んだ。二千円と言わなかったことに、少し後悔を覚えながらも小躍りしながら立ち上がろうとすると、
「ちょっと待て!!」
「まだ話がある。小遣いは値上げしてやる。だが、その代りな!!」と言われ、また正座した。
いつの時代も、子が親に、金をせびると、親は「その代りな」という条件をつける。
このフレーズは、昭和も平成も変わらない。いや、きっと江戸の昔からも同じだと私は思っている。
—てなことで—
その条件が提示された。
「明日から本堂の掃除をしろ!!学校に行く前でもいい。帰ってからでもよい。」
「それと、本堂にある線香立ての灰(あく)おろしをせよ」
「そうしたら 千五百円に値上げしてやる。」
こちとらは、目の前の五百円が欲しくて、欲しくてたまらない。
間髪入れず…。
「ハイ、やります。」と答えたのであった。
「そうか、やるのか。」父親和尚は、意味有りげな笑いを浮かべた。
実は、この笑いの意味を思い知らされたのは、次の日のことであった。
私は、学生服に着替え、ささっと本堂の清掃や、灰(あく)おろしを手早くすませて学校へ行った。
父親和尚は、私の帰るのを待ちかねていたのであろうか。
帰るやいなや「すぐ本堂に来い」と形相を変じて怒鳴られた。
訳も分からず本堂に入るやいなや
「この掃除の仕方は、なんじゃぁ〜」
「この線香立ての灰(あく)おろしは なんじゃぁ〜」
「なっちょっらん」
「もう一度 やり直せェ〜!!」
あの五百円と引き換えの「その代りな」という甘言は、実は、恐ろしい禅寺小僧の修行の始りであったのだ。
毎日、学校から帰ってくると、また怒られる。
「何じゃぁ〜これは!!」
「なっちょっらん」
—また、やり直す。—
—また怒られる。—
そんな日々が何日か経った時、「何で あんなに怒るのだろう?」と思って、掃除した後、本堂や線香立ての回りの様子を見てみた。
—その時—
ハッと気づかさせられたことがあった。
本堂の畳の上には、小さなゴミが浮んで見える。線香立ての回りは、線香をおろした後の白い灰(はい)がそのままであった。
「おとちゃん。分かったじゃ!!」
「オラ、ちゃんと掃除していなかったし、灰おろしの始末もしてなかった。」
—そしたらである—
父親和尚は「そうか」と頷くと、すっくと立ち上がり本堂へ向かった。高校生の私も後について行く。
「掃除というものはな。畳の目に沿って箒(ほうき)で掃き切ることが大切じゃ」
「灰はな!!静かに、小さく振るい落とし、灰を舞い上げない」
「そして 燃え残った細い線香を取り除いたきれいな灰は、こうやって『灰ならし』で真っすぐに引くのじゃ」
父親は、初めてやって見せてくれた。
—なるほど—
きれいな線の紋様であった。しかも水平だ。「やってみろ!!」と言われ、私がやると、波打ち、しかもくねくねと曲がってしまっている。
「心が込もらず、アレコレ考えながらやっているから波打つんじゃ」
「しっかりと心を込めて掃除せよ」
これは、まさに掃除ばかりではなく、禅の修行の肝要たるものであった。
父親和尚は、私が何が悪いのか、怒鳴られている理由を、私が気づくまで待っていたのだ。
ただ教えるのではない。分からない者が気づいた時に教える。
教えてから、やらせるのではない。やらせてから教える。それが禅寺流の修行の教えだった。
—事実—
それから、朝の掃除の仕方が変った。
身を入れ、心を込めるようにして、本堂の掃除をした。
2月の寒い寒い朝であった。昔の古い木造本堂の畳の上は、まるでスケートリンクの氷の上を裸足で歩いているようなものである。
この寒さに耐えながら足の冷たさを感じながら箒で掃いていた時のことである。
突如として、こんな俳句がひらめいた。
「厳寒(ごんかん)に 我(わ)が身(み)を投じて 無心(むしん)なれ」
それは、寒くてしょうがなく、この寒さから逃れたいという気持で、無心になれば足の冷たさを感じないであろうというぐらいの句であった。
掃除を終ると、その思いついた俳句を茶の間の父親和尚の机の上にある半紙に書き置いて登校した。
帰ってくると、いきなり茶の間に呼ばれた。
「このヘタな俳句らしきものは、お前が書いたのか?」
私は、また怒鳴られると思い、身をすくめ「ハイ」と小声で答えた。
すると、その半紙を天にかざしながら、
「ふ〜ん!!お前は、和尚になれるかもしれないな」と呟いた。
それから1ヶ月後の3月24日、私は和尚となるべく「得度式(とくどしき)」が行われ、それまで「モトノブ(元延)」と呼ばれていた名は、同じ表記ながら「げんえん(元延)」と改められた。
不言和尚は、和尚としての機の熟するを待っていたのであろうか?
それとも私はまんまと父親和尚の策略に乗せられたのであろうか?
今思い返すに、あの「五百円値上げ」が、私としての和尚の道、そして仏道の第一歩であり、あの駄句なる「厳寒に 我が身を投じて 無心なれ」は、まさに小僧たる和尚としての「初発心(しょほっしん)」であったことは間違いない。
合掌