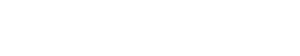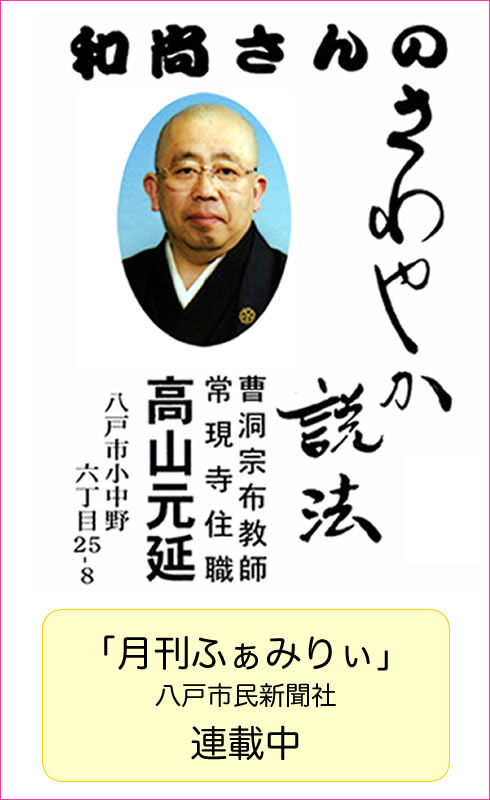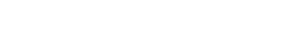和尚さんのさわやか説法247
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
「和尚さん!!この頃、何だかお経の唱え方が変わってきたよ!!」
ある壇家さんの訴えに、私はギクッとした。「えっ?どんなふうにですか?」
「それで、私の御経はほんつけない御経になってなってるんですか…?」(涙)
私は、うなだれてしまった。それはあながち思い当らんことがなきにしもあらずだからだ。(※読者の皆さんは、アレコレ詮索しないで下さいね。💧💧💧)
—ところが—
その檀家さんは、まるっきり逆のことを言ったのだ。
「いやー。一皮むけたというか。以前の御経とちがって、張りがあるというか、朗々と聞こえるんだよ」
「それに味が出てきたっていうか。ともかく違うんだよぉっ」
私は思わず「じぇっ、じぇっ、じぇっ」と叫んでいた。
(あまちゃんの影響を大分受けています💧💧💧)
—実は—
私自身も、味はさておいて、御経の唱え方が変わってきたとの自覚はあった。
それは、こんなことがあってのことだ。
今年の新年早々、「青森刑務所」から一本の電話があった。
「今度、刑務所内の新年カラオケ大会がありますが、できれば、その審査委員長をやってもらいたいのですが…」
「えっ!!私がカラオケの審査をするんですかあー?」
「それも委員長なんて出来ませんよぉ」
「私はカラオケというよりカンオケの方なんですが」とバカなダジャレで丁寧にお断りをした。
—ところが—
「いやいや、和尚さんが、昨年暮れに受刑者達に講演をしてもらってから、皆なが是非とも来てもらいたいと、言うもんで」
というのも、私は「教誨師」(きょうかいし)という役目があり、罪を犯し刑に服している服役者に対し、「坐禅指導」を通して、彼らの心の安らぎと罪を懺悔(さんげ)し、社会に復帰するべくお手伝いをさせてもらっている。
今までは、平内町にある「青森少年院」の担当で、青少年の教誨をしていたが、そこは少子化や諸般の事情で閉鎖されることになった。
そこで配置換えとなり、刑務所の成人担当になった。ここは少子化とは逆に高齢化で、人数は増加している。
ということから、受刑者への顔見せということで全体講演をしたのであった。
—てなことで—
結果的には「カラオケ大会」の審査委員長にはなったのはいいが、どんなふうに審査すればいいのか、その基準たるものが分からなかった。
そこで、思いついたのが、北奥羽カラオケ大会の審査委員長を長年やっておられる小中野公民館の元館長である「船田勝美」氏に電話した。
船田さんは、事の経過を聞くと、「ブハーッ」と吹き出し、「和尚さんがカラオケの審査をやるってかー」
「和尚!!あんだは声はいいけど、歌はカラッキシ駄目だがらなぁー」と誉めてるのか、けなしているのか笑い転げるばかりであった。
「何とか、そのカラオケの審査の判定の仕方を教えて下さいよぉー」と電話口で三拝九拝をした。
—すると—
「まず、態度だね。しっかり歌おうとしているか。その歌に対する姿勢と心を見極める」
「それと楽しく、歌に愛情がこもっているかだ」と言い、次に具体例としてこう私に諭した。
「実際に歌の声を聴き取る時、母音(ぼいん)と子音(しいん)がハッキリ出し切っているかだ」
「母音、子音、の区別は分かりますか、和尚さん?」
「ハイ、母音は『あいうえお』であり、子音は『かきくけこ、さしすせそ』のことでしょ」
「その通り、歌を歌う時、この母音が重要なんです。例えば、千昌夫の『白樺、青空、南風…』と歌うとすれば、「しらかば」と単純に歌うのではなく「しらかばぁ…あー」ときちんと「あ」の母音で歌い切ることが、そのポイントなのだ。」
私は妙に納得してしまった。
「なるほど、母音を大切にし、母音で歌い切ってるかぁー」
—だが—
その教えの通りを基準として、カラオケ大会に臨んだのはいいが、受刑者の皆さんは、全員が上手なのである。
判別がつかないのだ。
ある者は演歌を感情を込めて、ある者はEXILEをリズミカルに、ある者は踊りながら楽しそうに……。
—もう—
私は母音も子音もぶっ飛んでしまい、それぞれの判定項目に高得点をつけるしかなかった。
やっぱり、これは歌をきちんと聞くべく審査の能力の違いに他ならないと絶望感的心境に落ち込んでしまっていた。
それでも、そのカラオケ大会は審査委員長の能力は別として、楽しく盛会裡に終了した。
—しかし—
暗澹たる気持で帰途の新幹線の中で、フト気づかされたものがあった。
それは、母音(ぼいん)で歌い切るというのは、『御経』にも言えることではないか。御経も声に出して唱えるという意味においては、歌と同じではないか。ということであった。
そこで、早速、お寺に帰ると、本堂に直行し「般若心経」を唱えた。勿論、母音と子音をキチンと唱え切ることを意識してだ。
『般若心経』は古代インドより玄奘三蔵法師が中国に伝え、それを漢訳してから、ずうっと不変であり、その時代より数限りない僧侶あるいは一般の方々も唱えている。
しかし唱え方は各々個人個人で千差万別だ。
私自身、『般若心経』を唱えたのは、和尚となるべく決心した高校3年生の時からであり、現在まで毎日、唱えている。
—その時だった—
私は母音、子音を意識して唱えた時、突如として脳裡に浮んだのは、師匠でもある父親和尚から初めて『般若心経』の唱え方を教わったときのことだった。「御経はな、一文字一文字を丁寧に読むことなんだ。」
「しっかりと読み切ることが大切なんだ」と。
「初心の弁道(べんどう)、即ち本證(ほんしょう)の全体なり」
この言葉は道元禅師が『正法眼蔵』の中で説かれている禅の本質である。
「初心」たるその心と修行は、悟りという本證そのものであり、全体なのだという。
私にとって、高校三年生の時の「初心」が40年を経て、今の私の「初心の般若心経」へと成長した。
初心は本證でもあるが故に、いつまでも初期や初心者のままの「初心」ではない。初心は成長し、その時々(ときどき)にあって純真(まこと)なる心であり、本心なのだ。
このことを、室町時代に「能」を大成させた「世阿弥」は、その指導書たる『花鏡』の中で
「ぜひ初心忘れるべからず」
「時々(じじ)の初心忘れるべからず」
「老後の初心忘れるべからず」
と、3つの「初心」について語る。
「初心」は成長させるものであり、成長してこその「初心」なのだ。
それはとりもなおさず「本證の全体」だからだ。
—事実—
私の御経の唱え方は、変わったように思える。母音を出し切ることによって、その音域は朗々として、深みを増してきた。
あの時の師匠の教えは「老後の初心」たる『般若心経』だった。
私自身、これからは同じく
「老後の初心忘れるべからず」で、時々の「初心」に立ち返り成長させていかねばならないのだ。
読者の皆様も今の「初心」、時々の「初心」、老後の「初心」を忘れるべからずである。
それを願ってやまない。
合掌