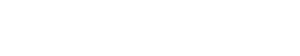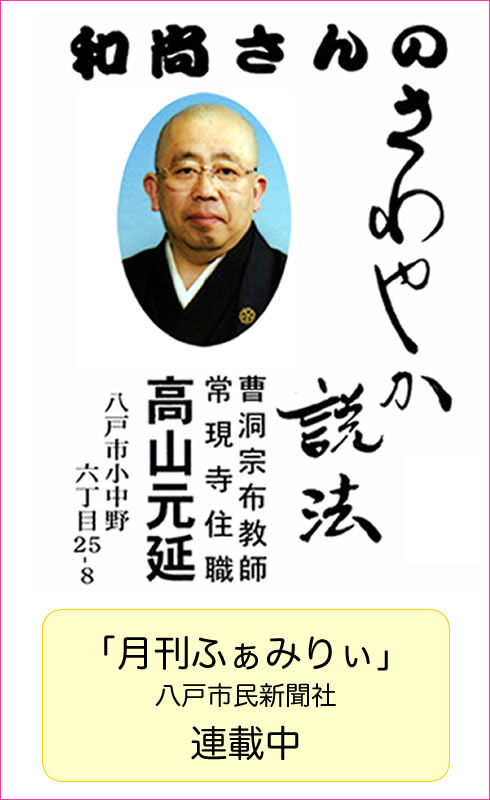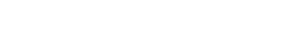和尚さんのさわやか説法239
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
先日10月5日は、かの「ダルマ」さんが亡くなられた日であり、「達磨忌(だるまき)」と称せられる日であった。
つまり、ダルマさんの御命日なのである。
そう聞くと、「えっ?まさかぁ?あの縁起物とか、置き物、土産物など、赤い張子のダルマさんって、生きていた人なんですか?」とビックリすることであろう。
—そうなのである—
実在の人物で、ダルマは「達磨」。あるいは古くは「達摩」と漢字で表記され、今から約1500年前の方であり、示寂したのは諸説あるが、西暦532年(宇井伯寿説)、150歳であったと伝えられている。
掛軸にも描かれている眼光鋭くギロッと睨む達磨大師は、出生は南インドの香至王国の第3王子で、後に中国に渡り、禅の教えを初めて広められたことにより、「禅宗初祖」として尊仰(そんごう)されている。
その達磨大師が若き王子の頃、仏道に入ることになったのはこういう機縁があったからだという。
それは、ある日、お釈迦様の仏法を継承した第27代目の祖師である「般若多羅(はんにゃたら)尊者」が香至王(こうしおう)のもとを訪れた際、国王は光輝く宝珠を与えた。
その時、尊者は3人の王子に「この宝珠にまさるものは、この世にあるだろうか?」と問うと、兄の王子達は「これにまさるものはない!!」と答えた。
しかし、第3王子だけは「物である宝珠より、仏陀(ブッダ)の智慧の方がはるかに勝る」と答えたのであった。
それを聞いた尊者はハタッと膝を打ち、ニッコリ笑われて、その王子を弟子として受け入れ、やがて第28代目の祖として「菩提達磨(ぼだいだるま)」(ボーディダンマ)という名を授けたというのである。
その後、般若多羅尊者が亡くなられるまで側につかえ、師の亡きあと、60歳の頃に中国に「仏法」を伝えんが為に渡ることを決意した。その達磨大師の伝えた仏法は、尊者より受(う)け嗣(つ)いだ「禅の教え」であったのだ。
あの「丸型」のダルマさん。あの「起き上がり小法師」のダルマさん。七転び八起きのダルマさんは、実は「坐禅」の姿と心を具象化したものであった。
脚を組み、両手を組んでのシルエットは、「坐禅」をしている姿であり、転んでも起き上がるというのは何事にも動じない「不動」なる「坐禅の心」そのものなのである。
その達磨大師が、インドから初めて中国の地を踏んだ時、師の名声を聞き及び、当時、南中国の国主であった「梁(りょう)の武帝(ぶてい)」という王が、是非にも会いたいと切望した。
それは武帝(ぶてい)は、多くの堂塔伽藍(がらん)を造立し、あるいは沢山の僧侶を庇護しては篤く仏教に帰依していたからである。
武帝は会うやいなやこのことを話し「私にはどれほどの功徳が有るのだろうか?」と、いかにも鼻高々に問い尋ねた。
このインドから渡来した28代目の尊者は、きっと驚嘆し、自分の功徳を称讃するであろうと期待していた。
その問答の事実が、これだ!!。
「帝(てい)問(と)うて曰(いわ)く、朕(ちん)、即位(そくい)して已来(いらい)。寺を造り、経を写し、僧を度(ど)すこと、あげて記(き)す可(べ)からず。(数えきれないほど)何(なん)の功徳(くどく)有(あ)りや!!」
「師(し)曰(いわ)く 無功徳(むくどく)!!」
功徳なんか有りませんよ!!無功徳なりと、武帝の問いを喝破したのである。
これには、国主の武帝は、おったまげたのなんのって!!
自分には、大いなる功徳が有ると思っていたにもかかわらず、ギャフンとさせられてしまった。
—しかし—
この「無功徳」の達磨大師の答えは、実はただ単に厳しく言い放ったものではなく、もっと実に深遠なる「禅の教え」だったのだ。
達磨大師は武帝の心を、しっかりと受け止め、真(まこと)の「功徳」のあり方を教えたかったにちがいない。
仏教の帰依とは、功徳を求めるものではなく、ましてや見返り的なものを望むものではないということを。
「帰依」というその心と行い自身に、すでに「功徳」は、そなわっているのであり、そこに「有る」とか「無い」とかに、執着してはならないのである。
それは、経を写し、読むことも、また坐禅に作務、托鉢にしても全ての仏道修行には、功徳は、そのままにそなわっている。
だからこそ、そこに功徳を求め、有る無しとしてはならないのであった。
そのことは、仏道修行だけではなく、私達の日常の行いもまた然りである。善行もボランティア活動にしてもそうなのだ。
達磨大師は、その「有るか無いか」との、こだわった武帝の心を喝破し、その執着心を戒めたのである。
あの「無功徳」の「無」は「有無相対」の価値観の心、あるいは「有る」と心が動き、「無し」とも心が動く、その揺れ動く心を否定した「動ずること」のない「不動の功徳」ともいえるのだ。
ということは、「無功徳」とは、有無相対を超越した「絶対無」であって、「無なる功徳」あるいは「無の功徳あり」とも解釈できる。
まさしく、達磨大師の「坐禅の姿」であり不動なる「坐禅の心」であったのだ。
それを大師は武帝に気づいてもらいたかったのではなかろうか。
—ひるがえって—
冒頭の達磨大師が、若き王子の頃、般若多羅尊者との初想見の時、「この宝珠にまさるものはあるだろうか」とのエピソードを思い出してもらいたい。
王子の「物の宝珠より、仏陀の智慧がまさる」との答えを。
つまり、達磨大師は宝珠という物のあり方に執われず「仏陀の教え」そのものを尊いとしている。
達磨大師は若き時代より、それは確固としてあったのだ。
その昇華した言葉が「無功徳」なる「喝(かつ)」であると私は思う。
私は今、あらためて、この「さわやか説法」を書きながら達磨大師の説かれている「心」を学んだ。
—かく考えるならば—
私、高山和尚なんぞは、真っ先に達磨大師からお叱りを受けるであろう。
「お前ぐらい、功徳を求める者はいない!!」「あっちや、こっちと求めてばかりいる!!」「しっかりと不動なる心を見据えよ」と…。
しかしながら、私は、達磨大師の教えも分からず、「ダルマさん」を棚に飾っているだけなのだ。
それゆえなのであろう。いつも私は「七転八起(しちてんはっき)」ではなくして、「七転八倒(しちてんばっとう)」の中で悶え転げ回っている。
合掌