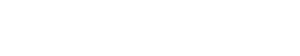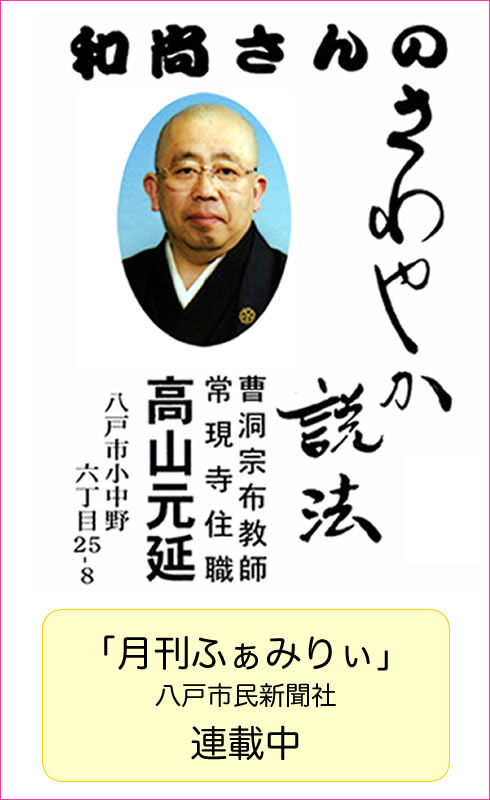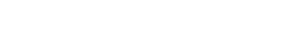和尚さんのさわやか説法202
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
「へェーへぇっくしょん!!」
万吉は思わず、大きなくしゃみをした。
「誰か俺の噂してるんだべが」
万吉は南部なまりでそのくしゃみのあまりの大きさの故に驚いて、心の中でつぶやいた。
「へェーへぇっくしょん!!」
万吉は、また大きいくしゃみをした。
さあ、「芝居版ぼくざん物語」第二幕の始まり始まり。
万吉が今いる所は、そう!!花のお江戸は、天保13年の時代だ。
「真夏の土用というのに、くしゃみをするってぇのは、こりゃ、お前さん。
誰かが、悪い噂をしているんじゃねェーのかい」
キレのいい、江戸弁で話しかけたのは、漢学者の菊池竹庵先生であった。
「はァー、ワシもそう思いますじゃ」
まだ南部なまりの少し残る口調で万吉は答えた。
それもそのはずである。そのくしゃみの原因は、遠く600㎞も離れた南部は
湊村の生家「うんど屋の井戸端」からであった。
悪い噂なんかじゃない。万吉のことを話題にし、いつも心配している父や母、
そして近所のおばさん達の「思い」であったのだ。
「おい。お前さんは笹本金英って名前なのかい」
「はい、そうであります。お師匠様のお名前から一文字いただいて金英といいます」
「どうぞ、今日から御講義の程よろしくお願い申し上げます」
—そう—
万吉は、もう万吉という名前ではなく、僧名を「金英」と言うのであり、
また「西有」とも名のっていなかった、青年時代のことである。
この金英和尚の目の前にいる菊地竹庵(きくちちくあん)なる漢学者先生は、幕府立(官立)の昌平校(しょうへいこう)を卒業し、松本藩(長野県)の儒学の指南をした学者であり、今は金英和尚が修行する「旃檀林(せんだんりん)」の門前で漢学の看板を立てていたのである。
金英和尚は、旃檀林(せんだんりん)で仏教学を勉強するにあたって、禅籍を読解するには何よりも漢学の基礎を身につけなければならないとのことから、この竹庵先生の門を叩いたのであった。
その時、まさに真夏の土用であった。
竹庵先生は、上半身、裸で団扇をバタバタさせながら、そのくしゃみの主である金英を見つめて、思わず「ワッハッハ」と声を出して笑った。
それは、金英和尚の姿格好を見て、これは絶対にくしゃみをするわけはないと、思った。くしゃみをするということは、これは噂以外にありえないと確信したからであった。
「おい!!お前さん、暑いだろうに。何で綿入れなんか着てるんだい?」
「はい、暑いであります。でも、私はこれしか着物を持っておらず夏も冬も一緒であります」
そう言って、金英は汗をポタポタを流しながら、真面目に答えた。
「そうかそうか。」と竹庵先生、頷くも、このくそ暑いのに、よく耐えられるなと
感心するやら、気の毒に思いながらも笑いがこらえきれなかった。
「ウフッフ、綿入れ一枚か…」
「そうだ!!妙案がある。その綿入れを表と裏と二つに分けてしまえばよいではないか!!」
「それで、中身の綿を取って、冬になったらまた、もとの一枚にするんだよ」
「先生!!まことに妙案であります。夏は二枚の着物で、冬は一枚でありますな」
「そうじゃそうじゃ。ワッハッハ」
金英も、先生の高笑いにつられて、アッハッハと声を立てて笑った。
この時、まさに師匠と門弟の「気」が「?啄同時(そったくどうじ)」。
一瞬にして通じ合ったのであった。
「こいつは、なかなか見どころがある青年じゃわい」
「無邪気で純真(じゅんしん)なばかりではない。この揺らがない構えといい、
眼光の輝き。それでいて妙に人を惹きつけるところがある」
「将来、どんな和尚になるか。教えがいがあるかもしれんぞ」
こう心の中で呟きながら、金英和尚に尋ねた。
「さっきお前さんの名前は師匠から一文字もらって金英と言ったな」
「じゃあ、お師匠様は何て言うんだね」
「はい!!金竜(きんりゅう)様と言われます」
「そうか、金竜と言うのか。ところで、どんな御師匠様だったのかな」
竹庵は咄嗟にひらめいた。
「こいつの師匠は多分に大力量底の人物じゃろう。」
こいつの人物を見るには、師匠のことを聞くのが一番であろうと思った。
「はい。御師匠様は、私の家の菩提寺の住職でありまして、私が13才の時、天保4年に得度したのであります」
「厳しくもあり、やさしくもあり、とてもおもしろい方でもありました。」
「なるほどなるほど。面白いとな。どんなふうなのか、ワシにも聞かせてくれんか?」
「はい。こんなことがありました。門前に大変、鳥好きの爺さんがおりまして、方丈様の所へよく訪ねて来てました。それである日、『和尚様!!私が死んだら、どうぞ大好きな鳥に関係ある戒名をつけてくれませんかね。』と頼んだのです」
「ほう!!それで、その爺さんは亡くなったのかい」
「はい。亡くなりました。そしたら御師匠様は、こう戒名をつけたのです。
雁鴨白鳥信士(がんおうはくちょうしんじ)と。」
「なかなか、うまい戒名をつけたものじゃな。全部鳥の名前が入っておる。」
「そしてですね。引導を、こう渡したのです。」
「どんな引導じゃな?」
「はい。こうであります。
唐(から)にては鳳凰(ほうおう)を神鳥(しんちょう)として尊(とうと)び、
天竺(てんじく)の人(ひと)孔雀(くじゃく)を喜び
雁(がん)は長空千里(ちょうくうせんり)高(たか)きを飛翔(ひしょう)し、
鴨(かも)は山陰沼沢(さんいんしょうたく)に身(み)をひそめ、
白鳥(はくちょう)雪(ゆき)に一如(いちにょ)して飛(と)んで雲(くも)の如(ごと)し
大和(やまと)の国は陸奥(むつ)の里、
自淵山長流寺庭(じえんざんちょうりゅじてい)の梅(うめ)の花(はな)
鶯(うぐいす)法法法華経(ホホホケキョウ)の功徳(くどく)に依(よ)って
烏(カラス) 喝(かぁ)ーっ と、引導を渡したのであります」
「ワッハッハ。戒名もさることながら、素晴しき引導じゃな!!」
「まさに、機智円明(きちえんみょう)、当意即妙(とういそくみょう)、
禅機(ぜんき)あふるる風格(ふうかく)じゃ」
「なるほど、その御師匠様から剃髪(ていはつ)してもらい、小僧となって、お側につかえていたのじゃな」
「はい。師匠が亡くなるまで7年間ついておりました。」
「そうか。遷化されたのか。しかしながら、そのような気質は、お前さんにも備わっているようじゃな」
竹庵は、この金英に漢学を通して、心から育ててみたいと思った。
「こいつ田舎の和尚ながら、将来が楽しみじゃわい」
「仏教を学ぶ為に、まず漢学を徹底したいという心意気は大層なものじゃ」
「ワッハッハ。ワッハッハ。」
竹庵先生、汗をポタポタと流し、師匠の物語を懸命に話す金英をあらためて見直し、さも愉快そうに笑った。
—さてさて—
第二幕、江戸での穆山禅師様の修行物語!!
どんな風に展開していくのやら、次号をお楽しみに。
花のお江戸は
「えーど。えーど。」
私、高山和尚の機知はこのぐらいのレベル。まさに金竜様とは雲泥の差であります。
トッホッホ(涙)
合掌