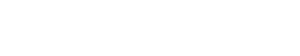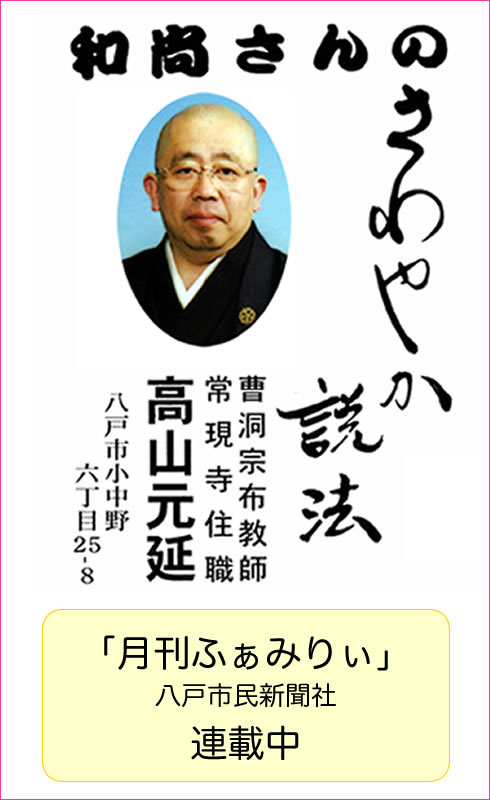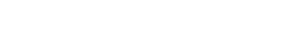和尚さんのさわやか説法196
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
新年明けましておめでとうございます。
皆様にとりまして、今年が良き年であることを御祈念申し上げます。
さて、年頭から、悪たれ川流之介が語る「それからの杜子春」の物語は、越年しての続きです。
昨年のパートⅣ12月号を読んだ方は、これは昔話の「鶴の恩返し」だなと思ったでしょっ。
—ちがいますよっ—
それは読んでからのお楽しみ!!
それでは始まり始まり。
杜子春は夕方、お千が納屋へ帰ると一歩も外へ出ず、朝まで何かをしている。それも、ここへ来て以来ずうーっとだ。もう3年の月日が経とうとしていたのだ。
今まで気になって、気になって仕方がなかったが、お千との約束したことでもあり、納屋の戸を開けることはしなかった。
—でも—
杜子春は、どうしても開けたくなった。意を決してガラッと開けた。
「こっ!!これは!!」
杜子春は、その場に腰が抜けたかのようにヘタリこんでしまった。
納屋には、なんと何百という小さな観音様が輝いていたのだ。
「お千!!お前は…!!」
「杜子春様!!戸を開けたのですねェー」お千はキッと睨み返すと、涙が頬をつたわった。
「あれほど、納屋の扉を開けてはなりませぬと約束をしたのに」
「いっいや!!すまない。おっ俺は、お前がこの納屋に入ると、何やら称える声や物を刻む音がし、一体?何をしているのだろうと思って!!」
「杜子春様!!今日は私が、こちらへまいりまして千日目であります。」
「そして、今日が千体観音像満願の日でありました。」
「なっなんと!!お前は、毎日、観音像を彫っていたのかぁー。」
「はい!!私は3年前の戦さで父と母を亡くし、また、あの地獄のような戦場でたくさんの人々が死にました。」
「私は、父母(ちちはは)や苦しんで死んでいった人達を観音様のもとで幸せになってもらいたいと思いました。」
「そっそれで、お前は毎日、お経を称え、観音様を彫っていたのか?」
「はい!!もしかすれば父母(ちちはは)は地獄で苦しんでいるかもと思えば、どうしても、そうせざるを得なかったのです」
この言葉を聞いた瞬間、杜子春はワナワナと震え、あの光景を思い出した。
—それは—
杜子春が仙人修行の時のことであった。絶対に口をきいてはならぬとのことから地獄に落され、そこで父と母に出会った時のことである。
母は鬼にムチ打たれ倒れながらも息たえだえに「杜子春や!!私たちはどうなっても、お前が幸せになれるのなら…」と。
あの母の声を聞いた途端、杜子春は思わず母の名を叫んだことを。
杜子春はお千に、これまでのことを、ありのままに語った。
「お千!!俺は仙人に修行を諦め『人間らしく生きたい』と言った時、仙人はこの泰山の家を与えてくれたのだ。」
「おっ俺は、一生懸命働いたが、自分のことばっかり考えていた。」
杜子春は慟哭した。「おっ俺はぁー。亡くなった父母(ちちはは)を地獄に置き去りにしたままだったぁー。」
「母は俺に幸せになってくれと言ってくれたのに、俺は父母(ちちはは)の『あの世の幸せ』を考えてはいなかったんだぁー」
「父母(ちちはは)を救おうとすることに気づかなかった。いや、気づこうともしなかった。嗚呼ゝ」
この慟哭を仙人は天上界から見つめていた。
「どうやら、杜子春は人間の人間らしい心というものに気づき始めたらしいのぉ」と、ニコリと微笑(ほほえ)まれた。
「お千!!私にも観音様を彫らせてくれ!!」
「はい!!杜子春様。この千体満願の観音様を一緒に彫りましょう。私の父母(ちちはは)の為に、あなた様の父母様(ちちははさま)の為に」
お千と杜子春は、一緒に懸命に彫った。その観音様は二人の涙で濡れていた。
「出来たぁー。お千!!彫り上げたよ!!」
最後の一刀を観音像の眼に入れた時、杜子春は思わず叫んだ。
「杜子春様、出来ましたね。笑みが浮かんでいる澄んだ眼の観音様です。」
—その時—
杜子春のいた納屋は千の光に輝いた(注:千の風ではありませんよ)。その光は、あの亡き父母がおわす地獄を照らした。
—なんと、その瞬間—
地獄は極楽浄土の世界に一変した。
杜子春の切なる願いは、父母を極楽に上らせたのではない。地獄そのものを極楽と化(け)したのだ。
父母を救わんとする願行(がんぎょう)は、他の苦しんでいる人々も一緒に救うことでもある。自分の父母だけではない。皆も一緒に救い、自らも救われることであった。
「杜子春やぁー。」「杜子春よぉー。」
母の声が、父の声が杜子春の心の中に聞こえたような気がした。
この有様をじっと天上界から仙人は見守っていたが、やがてお千を手招きした。
なんと!!その姿は、かの白髪の仙人ではなくして、お釈迦様であった。
「お千!!そろそろ天上界へ帰ることにしようかい。」
「いえ、お釈迦様!!私は杜子春様のお側にいとうございます」
「ナニ!!私は観世音菩薩のそなたを傷ついた鶴とならしめ、さらにお千として杜子春のもとに差し向けたのだが…」
「お前は観世音菩薩に戻ることなく、人間でいたいというのか!!」
「はい。私はお千のままで杜子春様と一緒に暮らしたいのです。」「私は杜子春様を愛してしまいました。」
お釈迦様は、しばし考えられておられましたが、ニコリと笑うと
「そうか、あい分かった。お前の好きにするがよい」
「ただし、お前は二度と千手千眼(せんじゅせんげん)の観世音菩薩に戻ることなく、普通の人間としての『お千』なんだぞ」
「はい。私はお千という人間として、人間らしく生きていきとうございます」
「そうかそうか。杜子春と一緒にな。では!!さらばじゃ!!」
杜子春は眠っていた。目が覚めると、あの千の光に輝いていた納屋は、昔の古ぼけた納屋のままだった。
「アレ!!おかしいなあ。あのたくさんの観音様は、どうしたんだろっ」
「それにお千は?」
杜子春は目をパチクリしながら、あたりを見渡した。
「夢だったんだろうか」
不思議に思いながら、ふと、木机の上を見ると一体の小さな観音様が横たわっていた。
「こっこれは!!確か俺とお千が一緒に彫った観音様じゃ」
「すると!!昨日のことは夢ではないぞ」
「でも、この納屋は昔のままじゃ」
不審(いぶかし)そうに首をひねっていると…。
「杜子春さまぁー」と呼ぶお千の声が聞こえてきた。
「そうじゃ、お千は、お千はどこにいるんじゃ」
「杜子春さまぁー」畑の向こうから、お千が走ってくるのが見えた。
「おせん!!お千!!」
二人は、かけ寄った。
「杜子春様、お千は戻ってまいりました。」
「戻ってきた?どこから戻ってきたのじゃ」
「ううん。どこからでもいいのです。私は杜子春様の側にいたいのですから」
「えーっ。そうかぁー。俺だって、お千の側にいたいよ」
杜子春は思わずお千を抱きしめた。
「痛いです。杜子春さまぁったら。」甘えてお千は言った。
—そしてこう思った—
「人間って いいな」ってね。
納屋にもどると、二人は、一緒に彫った観音様の前で、お経を唱え、お互いに父母(ちちはは)の幸せを祈った。二人の澄んだ声は泰山の麓(ふもと)を、いやそればかりでなく天上界にも、極楽と化した地獄も響いた。
「お千!!俺は、何だか今、幸せだ。何か心が安らぐんだよ。」
「そうですか。それはよかったですね。きっと杜子春様は、とても素敵なことに気づかれたのでしょうね」
「うん。俺は人間らしく生きたい。人間らしく生きて幸せになりたいと、いつも思ってた。」
「それで一生懸命働いていれば、いつかきっと幸せになれるんだと考えてた」
「でも、そうではなかった。努力して働いていれば幸せになれるのではなくて、幸せだからこそ努力することができるんだと思ったのさ。」
「杜子春様、すっごいー。私も幸せですよ。」
「人間らしくっていうのは、過去も現在も未来も関り合いながら、自然も人間同士も関り合いの『縁』の中で生きている。」
「だから、亡くなった父母も、お千も、皆なも幸せにすることによって、自分も幸せになれるんだ」
「それが人間としての自分が人間らしくなれるんだということじゃないのかなぁ?」
熱く語り掛ける杜子春を、お千は「うんうん」と頷きながら目を潤ませていた。
その光景を、天上界から、仙人ことお釈迦様も、頷きながら見ていた。
「やっぱり、杜子春は見どころがあったわい。」
杜子春とお千の住む泰山の麓は、新年の明るい陽光に照らし出されていた。
—めでたしめでたし—
合掌