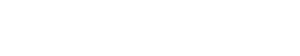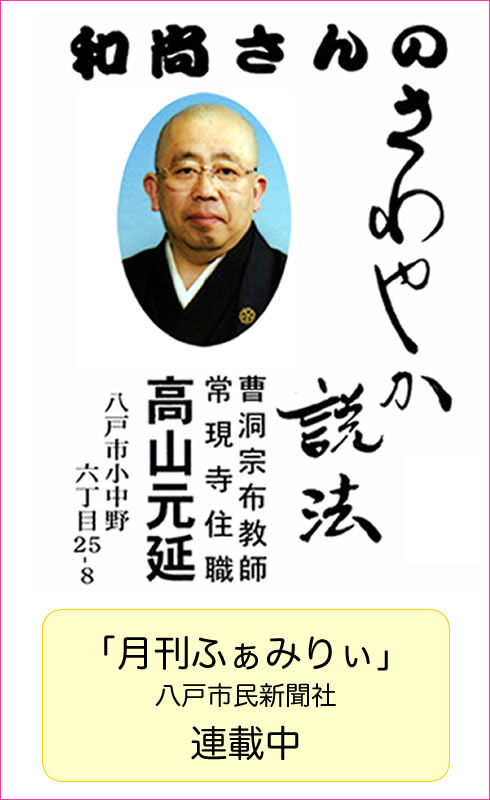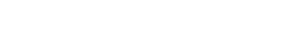和尚さんのさわやか説法195
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
今年も残すところ、後2週間。皆様は年の瀬を忙しくしておりますか?
はたまた忘年会で楽しく過ごしてますかな?
—さて— 先月号の続き…。
杜子春は、忘年会ではなくても「ちょっと一杯のつもりで飲んでェー」から、毎日のように夜の街へ出掛けた。
そして昔の仲間達と飲み歩いた。そのうち類は友を呼び、小金を持っている杜子春の所へ来ては、またぞろお世辞や追従を言い、おこぼれにあずかろうとした。
杜子春だってバカではない。以前の経験があるから、その世辞や追従を言うヤツラの魂胆も分かってるし気にもとめなかった。しかし、悪い気はしないのである。結構楽しかった。
—でも—
朝起きて酔いから覚(さ)めると、何か虚(むな)しく感じるのだ。楽しいことは楽しいのだが、どこか胸にポカッと穴が開(あ)いたような満ち足りることがなかったのである。
その時、きまって思い出すのが仙人との別れの時に誓ったあの言葉だ。
「何になっても、人間らしく正直なくらしをしたい」…。
「幸せになりたい」と。
南山のふもとのこの地に来て、田畑を耕し一生懸命働いている時に、いつも思ってた。
「人間らしく生きるんだ」「正直に生きていくんだ」と
「夜の街で一杯飲んでいる時だって、俺は思ってるよ。」
「人間らしく、正直になって生きたいって」
杜子春は自分の心に問いかける。
「酒を飲んでじゃ、人間らしくないっていうのかよぉー」
「夜の街で仲間達と楽しくやってるのは、正直でないっていうことなのかぁー?」
まるで、私、高山和尚が奥様に言い訳しているような杜子春の自問自答であった。
—読者の皆さん!!笑わないで下さいね。
私は、杜子春を私の代弁者に仕立てようとしてるのではないのですから—
杜子春は葛藤する。
「人間らしくって、一体何なんだ」「正直って?」「幸せに生きるって?」
—だから—
杜子春は、以前のような杜子春ではなかった。酒に溺れるようなことはなく、汗水流して働くことの喜びは確かにあった。
一生懸命働くことが人間らしい暮らしかもしれないと思いはあったのだ。
その姿を、かの仙人は天上界から、じぃっと眺めていた。
「どうやら、杜子春は何かに気づき始めてきたようじゃな」
「杜子春が何に気づくか、楽しみじゃわい」
仙人はフト何かを思いついたらしく、ニッコリと微笑まれた。
とある日、杜子春の家の前に傷ついた一羽の鶴が舞い落ちてきた。
「あれまぁー。羽に怪我をしてるじゃねェかぁー。可愛想に痛かったろうに」
杜子春は懸命に介抱した。傷口には、飲み残しの酒をかけて消毒し、薬草を塗り込め、何か滋養をつくものをと小魚を近くの川で釣ってきては食べさせた。
鶴は「クックッ」と喜び元気を回復していった。
次の日の朝、杜子春が起きて土間に行ってみると、なんと!!あの鶴は、もういなかったのである。
「あれまぁ。元気になって飛び立っていったのかな」
「よかったゝ。ちょっと寂しいけど。よかったわい」
何か杜子春は胸に安らぐものを覚えた。
—それから何日立ったのだろうか—
杜子春が畑で仕事をしていると薄汚れた姿の、どこか怪我をしているのか傷ついた女がころがり込んできた。
「助けて下さい!!私は隣の国の者ですが、戦さを逃れて、ここまでやって来ました。」
「お願いです。助けて下さい」
その女は杜子春に懇願した。
「そうか。わかった。では、私の家に来なさい。歩けるかな?さぁ、私の肩につかまって」
その女は家に着くと、どぉーっと倒れ、そのまま深い眠りに入った。
「よっぽど疲れていたんだろうなぁー。」
「そうだ、隣の国で内乱が起きたと言っていたなあ。」
女は、三日三晩眠りについたままだった。
杜子春が夕方、畑から帰ってくると、何やら美味しそうな匂いがしていた。
「お帰りなさいませ!!」
「あれまぁー。元気になったのかい。
「はい!!おかげさまで元気になりました」
「今日は、勝手ながら少しの御礼で夕餉(ゆうげ)の支度を致しました」
「なんとまぁー。大層な御馳走じゃのぉー」
それと、杜子春がもっとびっくりしたのは、あの薄汚れた女が、とても美しい若い女であったことだった。
「あっあんた!!あの女なのかぁ?」
「はい、さっき川に行き、汚れを落し髪も洗ってまいりました」 ニッコリ微笑むと、
杜子春は腰を抜かしてヘタリこんでしまった。
「私は、お千(せん)と言い、18になります。どうか私をしばらくこの家に居させてくれませんでしょうか」「お願い致します」
「いや!!それは!!」杜子春は手を横に振った。
「あなたは若い女性だ。こんな、むさ苦しい男の家にいるなんて」
「私は、あの納屋でよろしいんです。戦さが終わるまで、どうか」
杜子春は根負けしてしまった。
「あい分かった。じゃあなたの気がすむまで居るがよい」
その日の夕食のナントうまかったことか。杜子春はいつも一人ぼっちだった。この家で初めて誰かと食事したのである。
次の日から杜子春とお千は畑を耕し、仕事に精出した。昼は草むらに腰をおろし、弁当のお握りを分け合って食べた。
山から吹く風は心地よく、小鳥のさえずりも今までと違って耳をくすぐる。お千と眼が合うと何かニッコリとしたくなり、二人の笑い声が野山に響いた。
そんな日々が続いていった。
杜子春はフト「人間らしく生きるって、こういうことなのだろうか」と思った。
「お千と一緒にいると何かしら心が満ち足りてくる」
—しかし—
お千は夕食の片付けが終わると、そそくさと納屋に戻った。
杜子春とこんな約束をしていたのだ。
「私が納屋に入りましたなら、決して戸を開けてはなりませぬ。」
「どうぞ、そのことだけはお許し下さい。」と。
杜子春は、その約束を守った。しかし、妙に気になるのである。
ある日、納屋の側を通ると、何かしらお千の称(とな)える声がし、そしてコツコツと木を刻む音が聞こえてくるからだ。
「一体、お千は何をしているんだろう?」
彼女がきてから3年の月日が経とうとしていた。毎日が楽しく、夜の街に出ることもなくなった。あの追従や世辞を言う者達も寄りつかなくなっていた。
「昔、仙人に誓った、あの正直に生きるというのは、誰かの為に正直になれるということだろうか」
「まっすぐに生きていきたいという願いと行いではないだろうか」と、お千に思いを寄せ始めていた。
「しかし、お千は一体あの納屋で何をしているのだろう」
杜子春は、ある日の夜、決心をして納屋の戸に手をかけ戸をガラッと開けた。
—なんと—
そこには、まばゆいばかりの夥(おびただ)しい数の小さな観音像が輝いていた。
「こっこれは!!」
続きは、また新春の正月号で。またまた「悪たれ川流之介」が語ります。
皆様の来るべき新年が、まばゆいばかりの年であるよう祈念し、愛する人や家族の為に正直でありますように願ってやみません。
合掌