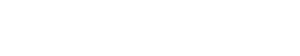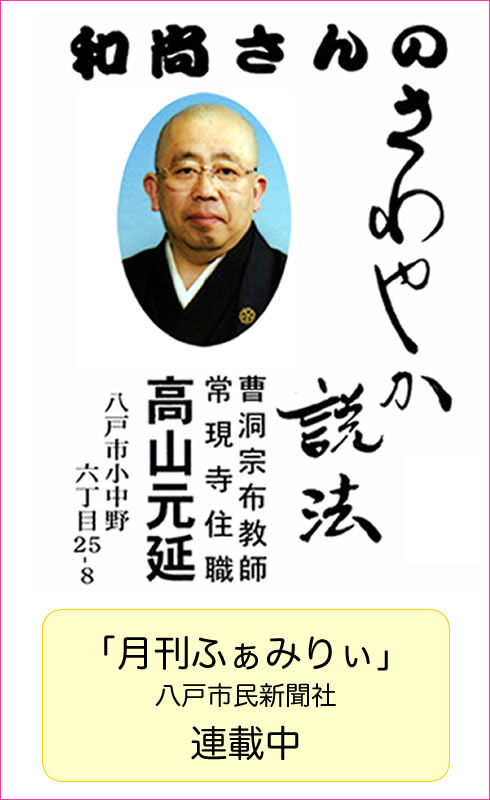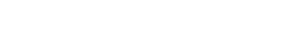和尚さんのさわやか説法194
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
私は、8月号と9月号で芥川龍之介の『杜子春』の物語を概説してきた。
ことの発端は、7月末、長者山新羅神社の境内で毎年開催されている「森のおとぎ会」において、その『杜子春』を集まった子供達に初めて実演し語ったことによる。
その時、私は、この物語はこのままで終ってしまっていいのだろうか?と自分自身に問い掛けていたのである。
この芥川龍之介の物語は、多くの方々も読み親しまれているものであり、私自身も子供の頃、読んだ記憶がある。
—しかし—
大人になってからというより、和尚になって、あらためて読み返し、おとぎ会で実演した時、どうしてもこの物語を完結させることなく続編を語りたくなかったのであった。
あれから杜子春は、どうなったんだろうか?と…。
杜子春は洛陽の西の門で仙人と出合い、夕陽に写る影の頭の部分を掘ってみるがいいとの指示通りにすると、一夜にして都(みやこ)随一の大金持になったが、またたく間(ま)に使い切ってしまった。
それも一度ならずも二度もだ。最初は影の頭の場所を、そして二度目は胸の場所を仙人の言う通りに掘ってみれば、宝の山だ。宝の山をあてこんでいろいろな人間が集まってきては、毎日が飲めや歌えやのドンチャン騒ぎ。あっという間にそれぞれ三年の月日が流れもとの黙阿弥となってしまった。しかし贅沢三昧をつくした杜子春を見捨てることなく仙人はまた現われ、三度目は、「腹の場所を」と言ってくれたが、彼は、それを固辞した。
その理由は、こうだった。
「もう、お金はいいのです。人間は薄情です。大金持になった時は世辞も追従も言うけれど、いったんお金がなくなると、誰も見向きもしません」
きっと芥川龍之介は人間社会の「人間」のあり方を、人間の薄情さを。いや、人間の本質性を追求したかったのであろうか。
もしかすれば、芥川自身を「杜子春」に重ね合わせて、世間の人間を風刺してのことだったかもしれない。
—そして—
杜子春は、もうお金はいらないが、今度は仙人になりたいと、申し出る。
常識的に考えるならば、「何!!言ってやがるんでェ!!」
「お前に宝の山を与えても使い放題のことをして、あげくは、言い寄ってきた人間達を薄情だと!!」「杜子春よ!!お前という奴は!!」と仙人は断るところではあるが、
芥川龍之介は、人間性の本質を追求せんが為であろうか。その要求を受け入れるのだ。
—しかし—
杜子春に仙人になるための約束を与える。
それは、「どんなことがあっても、絶対に口をきいてはならない」というものであった。
彼は峨眉山上(がびさんじょう)で魔性達の試練に耐えたが、命を奪われ、やがてその魂は地獄に落ちていく。
そこでも呵責に耐えに耐えて一言も口を開かなかった。業を煮やしたエンマ大王が、すでに亡くなっている彼の父母を引き出して、ムチで打ちすえた。
そして、倒れた母が「何も言わなくてもいいよ。それでお前が幸せになってくれるのなら……」と言う声にならない声を聞いた時、杜子春は思わず口を開き叫ぶのであった。
「おかぁ~さぁ~ん」と。
—すると—
杜子春は夢から覚めたかのように、あの洛陽の門の下にたたずんでいた。
やがて仙人が現われ「もし、お前がムチ打たれる母を見ていても一言も口を開かなかったなら、即座にワシはお前の魂の命さえも断ってしまおうと思っていた。」と、杜子春の母親を想う「慈愛」という人間的な「心」を見てとったのであった。
仙人は続けて言う。
「お前は、もう仙人になりたいとも望まず、大金持になることも愛想が尽きたはずじゃ」
「では、これからは何になったらいいと思うのじゃ?」
「はい!!何になっても人間らしい、正直なくらしをするつもりです」
この言葉は、芥川自身が最も言いたかったことにちがいない。それを杜子春の心として表わしたかったのだ。
仙人は、もう二度と杜子春に会うことはないと去ろうとしたが、振り向くとこう言った。
「おお!!幸いに、私は泰山の南のふもとに一軒の家をもっている。その家を畑ごとお前にやるから早速住むがいい」と愉快そうに、つけ加えて去っていったのだ。
それから杜子春はどうなっていたのだろうか?
それを、この私「悪たれ川流之助」が語ることにしよう。
三年の月日が流れた。なんと!!杜子春は、あの泰山の南のふもとの家で飲めや歌えのドンチャン騒ぎの毎日を過ごしていたのだ。
仙人から与えられた当時は、それはもう一生懸命、畑を耕し汗水たらして日の暮れるまで働いた。
その時いつも思うことは、仙人の前で誓った「人間らしく正直なくらしをしたい」との自分への言葉だった。
—しかし—
働いてゝ、少しお金がたまってくるようになると、妙に喉が渇くというか、胸のあたりがキュンキュンとしてくるのだ。
そう!!あの宝の山を掘りあてて皆なと一緒に、楽しく過ごしていた日々のことが忘れられないでいる「もう一人の自分」が胸の奥底に潜(ひそ)んでいたのだ。
ある日、杜子春は少したまった小金を持って街の居酒屋へ無性に行きたくなってしまった。
「チョット、一杯のつもりで飲んでェー」と植木等のスーダラ節のようになって、キューっと一気に飲みほすと、こりゃ!!まさしく至福の酒で、今までの胸のつっかえが落ちるが如くになったのだ。「うめぇーなぁ~」と
「俺は、あの時はあの時で楽しかったなぁ!!何でも自由に遊べて皆なとワイワイしていた。」「でも、今こうして一人で汗水たらして働いていることも、こよなく楽しい」
杜子春の心の中で葛藤が生じ始めてきた。
人間には誘惑に負けたくない気持ちと誘惑についつい誘われてしまいたくなる気持ちという相反する心が誰にでもある。苦労を自ら楽しみとする人間もいれば、逆に苦労せずして楽をして生きていきたいと思う人間もいる。
それは、どちらも人間の心であり、人間の本質性でもあるのだ。
そこへまた運が悪くというか、運命の糸がたぐり寄せられたのか昔の仲間が偶然にも、その居酒屋のノレンをくぐって来たのだった。
「あれまぁ!!杜子春じゃねェ~かぁ」
「おう!!お前かぁ~」
あとは推して知るべし。杯が杯を重ねてのドンチャン騒ぎだ。
杜子春は楽しかった。何もかも忘れるかのように楽しかった。
次の日また、杜子春は街へ出掛けた。
杜子春の心の中に、また昔の栄華がよみがえってしまったのだ。
—さあ、これから杜子春はどうなっていくのか—
この続きは、また来月号で!!
悪たれ川流之助が語ります。
合掌