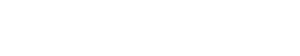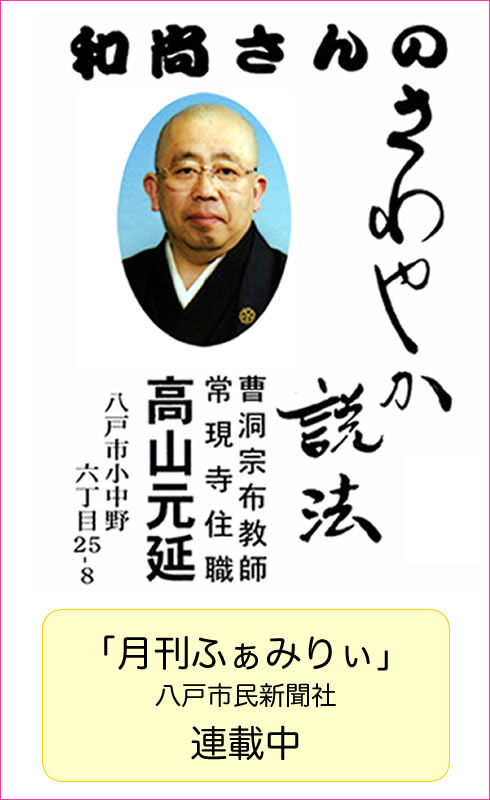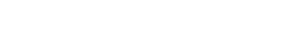和尚さんのさわやか説法165
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
先月号の「さわやか説法」で、私は芥川龍之介の「くもの糸」の朗読を聞いて、子供時代に読んだそれと、大人になり、あるいは和尚としての現在とでは、その印象の受け取り方が違っていることをもとにして書いてみた。
その印象の最もたるものは、「この物語はこのまま完結していいのであろうか」ということであった。
お釈迦様は、くもの命を助けたカン陀多(カンダタ)に思いを寄せられ、その糸を垂らした。彼は、それにすがり上がったが、途中で地獄の亡者たちが何百何千と、その細い糸に群がり上がっているのを見た時、「この糸は俺のものだぁー」と叫んだとたん、それまでどれだけの者がすがりついたとしても、何事もなかった「糸」が彼の手元でプツンと切れ、真っ逆様に落ちていったのだ。
それを見ていたお釈迦様は、どうなされたのか。
芥川龍之介は、作品の中の最終章でこう語っている。
「お釈迦さまは、極楽の蓮池(はすいけ)のふちに立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがてカン陀多が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになりはじめました。
自分ばかり地獄から脱け出そうとする、カン陀多の無慈悲(むじひ)な心が、そうしてその心相当(そうとう)な罰(ばつ)を受けて、もとの地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦さまのお目から見ると、あさましくおぼしめされたのでございましょう。
—中略—
極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。」
私は朗読を聞きながら、「ふーん、この物語は朝から昼までの間の物語だな」
「しかしよなぁ、その間、カン陀多も、よく頑張ったよな」と思った瞬間。
「お釈迦様は、この後(あと)どうなされたのか」
「もう、お釈迦様は、カン陀多を救うのをあきらめてしまったのだろうか」
「くもの命を助けたのは一回だったから、たった一度のチャンスを与えたにすぎないのですか」と、問い返したくなった。
—きっと—
お釈迦様は、その問に対して、こう答えられるだろう。
「私はね、カン陀多のことを『自分ばかりがぬけだそうとする無慈悲な者』と言ったが、このままカン陀多のことをあきらめてしまったらこの私が、最も無慈悲な心を持っていることになるだろうよ」
「慈悲というのは、たった一回や二回こっきりのことではないぞ」
「だから安心をし、カン陀多が救われるまで私は、ずぅーと糸を垂らすことになろうよ」
私は、思わずお釈迦様の「眼(まなざし)」に包まれたような気がした。
そして、こう心の中で思わず叫んだ。
「そうか、慈悲というのは、相手が気づくまで、救われるまで、苦しみから抜け出すまで続く、無限の心なんだ」
「そうなんだ、お釈迦様は、カン陀多に気づいてくれと願っているんだ」
「カン陀多よ!!気づいてくれ、カン陀多よ!!気づくんだぞ!!」ってね。
お釈迦様は毎朝毎朝極楽の蓮池のくもから、銀色の糸を垂らした。
カン陀多は、それを見て、また飛びつく。懸命に渾身(こんしん)の力をこめて上(のぼ)る。
ところが、中ほどまで上(のぼ)り、また下を見ては叫ぶ「この糸は俺さまのものだぁー」と、するとプツンと切れる。
—何回このことをくり返しただろうか—
—何日、上っては落ちただろうか—
カン陀多は考えはじめた。
「いつも叫んだとたんに手元で切れる」
「そうか叫ばなければいいんだ」「ようし、何も言わないで上ることにしよう」
—糸が見えた—
飛びついて上った。
今日のカン陀多は、何も言わないことを心を決めていたが、下を見て無数の亡者が同じように上ってくるのを見たとたん、また無性に叫びたくなるのだ。
「お前達、手をはなせ。俺の糸だぁ」と、
落ちて、また考えた。
「この無性に叫びたくなるのは何なんだろう」
「そういえば、俺は、生きている時も、そうだった」
「いつも俺はな、とか、俺だけが、とか、言っては、自分だけが満たされていればいいと思っていた。」
「人様のことなんか、微塵にも思わなかった」
「それが、たった一つだけ」
「そうだ、くもの命を考えた時があった。」
「その時、俺はお前にも小さな命がある。尊い命があると思って、殺せなかった」
—カン陀多は気づいた—
「生命というのは、俺だけのものではない。全てが生きて、皆な生きている生命なんだ」
「そうか、あのくもの糸は、俺だけの糸ではなかったんだ」
「皆なの糸なんだ」「だから皆な!!一緒に上ろうや」と叫べばいいのだ。
「皆なと一緒に上れば、下を見る必要なんかないんだ」
「今、この目の前の糸をしっかりとつかんでることが大切なんだ」
「ちゃんと、お釈迦様はつかんでくれてるんだ。」
「そういうことかぁ」
そう思ったとたん、カン陀多は身も心も、すとーんと軽くなったような気がした。
お釈迦様は「ニコッ」と微笑(ほほえ)まれた。
「やっとカン陀多は気づいてくれた」
「他の者も、気づいてくれればいいのだが」
とつぶやいて、花びらや小鳥達を極楽の蓮池から地獄へ使わした。
—そう—
実は、お釈迦様はカン陀多ばかりでなく全員を救いたいのである。
花の命を助けたものには花を、小鳥や動物の命を救った者には、それらを。
ところが、今までのカン陀多と同じように「俺の花びらだ」「俺の鳥だ」と叫んでは、すがりつく者達を追い払ったとたん、真っ逆様(まっさかさま)に落ちていったのであった。
それでも、お釈迦様は、毎日毎日、極楽から「ほとけの糸」を、「ほとけの小鳥」を使わしていたのであった。「一人が気づけば、同じく皆なが気づく」と「一人が極楽に上る心になれば、同事に皆なが極楽の心になれる」
「やっとカン陀多は、それに気がついてくれたわい」と、また、くり返しつぶやいて、今度はカン陀多が助けた「くも」をつまんで蓮池から糸を下ろさせたのであった。
その糸は、今まで以上にキラキラと輝いていたという。
—てなことで—
私は、かの有名な芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)の作品「くもの糸」に対し、悪口雑言(あっこうぞうごん)的に自説を書きつらねてしまった。
きっと芥川龍之介は私のことをこう言って断罪するだろう。
「高山和尚!!お前は、悪(あく)たれ川(がわ) 流之介(りゅうのすけ)だ」と……。
合掌