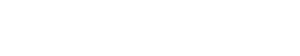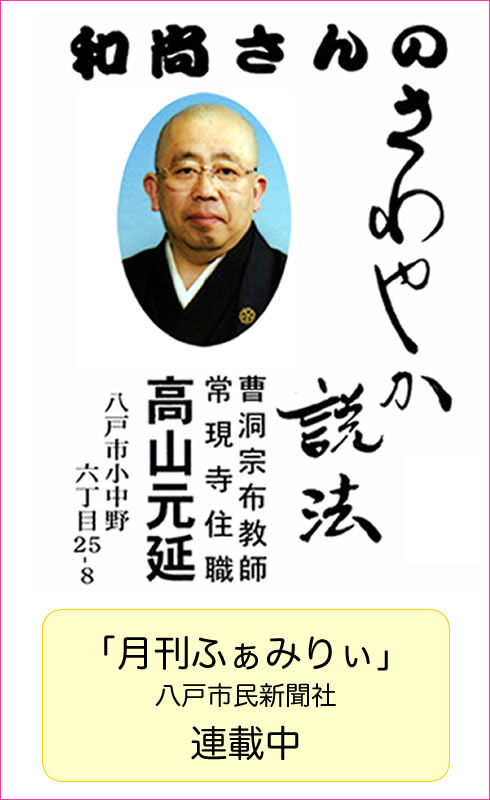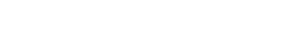和尚さんのさわやか説法166
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
「さわやか説法」8月号、9月号で私は、かの芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)の『くもの糸』を題材にして、勝手に自己解釈しながら、お釈迦様のカン陀多(ダタ)を救わんとする慈悲の心を通してカン陀多(ダタ)に何を教えたかったのか。あるいは何に気づいてもらいたかったのか、「悪たれ川、流之介」と化して自説を展開してみた。
そこで、こうなったなら、もっと「悪たれ川」になって、今月号もまた「くもの糸パート3」ということで歪曲(わいきょく)、猥雑(わいざつ)、ワイルドの限りを尽くして述べてみたいと思う。
—あれから—
—カン陀多(カンダタ)はどうなったのか—
前号でカン陀多は、こう気づいたと、書いた。「生命(いのち)というのは、俺だけのものではない。全てが生きて、皆な生きている生命(いのち)なんだ」
「そうか、あのくもの糸は、俺だけの糸ではなかったんだ」「皆なの糸なんだ」
「だから皆な!!一緒に上(のぼ)ろうよ」と叫べばいいのだ。と…。
「そういうことかぁー」
そう思ったとたん、カン陀多は身も心も、すとーんと軽くなったような気がした。
ここで読者の皆様はカン陀多は極楽に上(のぼ)りきったと思ったにちがいない。
—実は—
—なんと—
カン陀多は、まだ地獄の中にいたのである。
彼は、極楽へ上る「くもの糸」を自ら手を放ち、上るのをやめたのである。
—そして—
他の地獄の亡者達に対して、皆なを上らせていたのであった。
「さあ上がれ上がれ」
「決して、俺さまだけの糸だと叫ぶなよ」
「しっかりつかまって上っていけ!!」
「ちゃんとお釈迦様がつかんでくれているし救ってくださるんだ」
「迷わず、信じて上るだけでいいんだぞぉー」と皆なのお尻を持ち上げていたのである。
何たって、地獄の亡者達は無数である。無数ということは数限りが無いということである。次から次へとやってくるのであった。
カン陀多は皆なを激励しては「上れ上れ」と自らの力を尽くし、そのことを自らの喜びとした。
—きっとカン陀多は—
—ずうーと—
—いつまでも—
地獄の中にいるにちがいない。
ここまで私は、書いてきて、私の亡き父親和尚様の生前の口ぐせを思い出した。
—それは—
「俺はな、死んだら地獄に行く」
「地獄に行って、地獄の釜のフタになる」
「地獄の釜のフタになって、檀家さんや皆なが地獄に落ちてきたら」
「その釜のフタをしめて、極楽に送ってやる」
そう言っては、コップの酒をうまそうにグッとあおって上機嫌でいた、あの姿を。
—そうなんだ—
私は、今回の「くもの糸」を通して、カン陀多の心を述べてみて、あの時の「父親和尚の心」を初めて得心した。
父は、和尚として、「衆生を救わんとする心と行動」を自らを地獄に堕して、皆なを救いたいという「究極の選択」を自らに課していたのだ。
—では—
父はカン陀多と同じように、いつまでも、ずうーと、地獄にいるのだろうか。
父を地獄から救うことはできないのであろうか。
極楽に行かせることはできないのであろうか。
—それは—
私が死んだら、私が地獄に落ちて、父とバトンタッチすることが父親を地獄から救うことになるのだ。
私が父に替(かわ)って、私自身が新しい「地獄の釜のフタ」になればいいのだ。
そのことが父を極楽へ送ることになるんだ
—そう思うのである—
私が死んで父親と地獄で再会した時、きっとこういう会話になるだろう。
「おう、やっと来たな」
「方丈さん。お疲れさまでした。今まで大変だったね」
「何の何の、俺ももう年だし、少々疲れてきたわい」
「しかしなぁ、元延和尚!!お前も大分年とって、ここに来たなぁ」
「大丈夫かい。結構大変だぞ、地獄の釜のフタも」
「はい。方丈様も頑張ってきたんですから、私も頑張りますよ」
「さあ!!安心して極楽へ行って下さいな」
「そうだな、じゃあ、母さんも俺の来るのを待ちどおしいだろうから行くことにするか」
「では、さらばじゃ」と、いうことになるのではないか。
あのカン陀多も、父親和尚も、そしてお釈迦様、菩薩様の誓願は、人々を救いたい、人々を救わざるをえないという、強い願いと行動である。
では、なぜ救い、救わんとし、救度せざるをえないのであろうか。
その本質とは何なんだろうか。
それは、「わたしたちの世界」が「縁」によって起こる「縁起」の世界であるからである。
経典に「縁起を見るものは法を見る 法を見るものは縁起を見る」と説かれている。
ここでいう「法」とは「真理」であり、仏法であり、全ての存在ということである。
全ての存在は、相互につながりがあり、それぞれの縁によって、この世界を構成している。したがって、この縁によってつながる以外に独立した実体とか存在はありえないのである。
これは人間関係にも動植物の世界にも、そのほか、この世界を構成している一切のものに共通する真理であった。
—即ち—
かくなる縁起の法の上からの「わたし」や「わたしたち」の存在は相互に助け合い、救われていく「存在」であることは確かなことである。
だからこそ、自らを救わんとするには他を救い、他を救うことによって自らも救われるのである。
つまり、お釈迦様のあの「くもの糸」は上から降りてくるばかりではなく縦横無尽に繋がる「くもの巣の糸」でもあったのだ。
私は、今回の芥川龍之介の「くもの糸」を色々と脚色してみて、多くのことを学んだような気がする。
この「地獄、極楽」の世界は、あの世にあるというのではなく、実は私達一人一人(ひとりひとり)の「心」の世界のことなのだ。
誰しもが「お釈迦様」の心にもなれるし、「カン陀多」の心もある。
きっと、芥川龍之介は「自分の心」に「カン陀多」の心があることをわかっていて、カン陀多となって、あの「くもの糸」を書いたのであろう。
その芥川の上前をはね、名作(めいさく)を自説に曲解して展開したこの私、高山こそが「俺様のくもの糸」としたカン陀多そのものであった。
やっぱり私は「悪たれ川流之介」であることは間違いない。
合掌