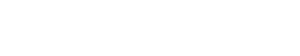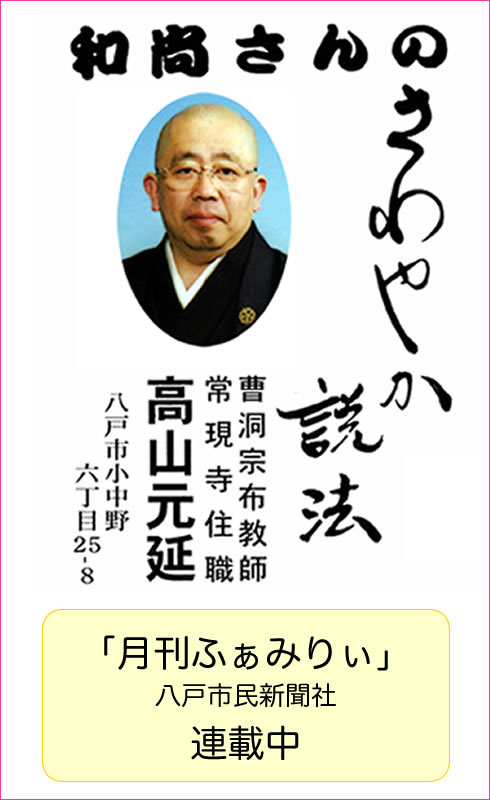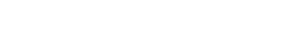和尚さんのさわやか説法193
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
私のペンネームは「悪たれ川流之介」だ。理由は、芥川龍之介をもじり、ただの一介の和尚であり、粗悪な文章しか書けなく、おまけに悪口雑言の説法のたれ流しだからである。
この名のもとに、私は平成16年に5回連続で芥川龍之介の『くもの糸』を悪たれ、先月号からは『杜子春』を流之介させて、それらの物語を自我自論で自己展開し、自己完結させようとしている。
まさに、希代の文豪相手にいどむ、身の程知らずの「芥(あくた)」(ちり)なる所業であることは確かだ。
芥川龍之介原作の『杜子春』を「このまま終わらせていいのか!!」と問題提起し、
「杜子春よ!!お前は、それでいいのか!!」との私の疑問から「こと」は始まった。
先月号は、杜子春が仙人修行の為「一切口をきくな」の戒めを守っているところに、魔性が現われ、かたくなに口を閉ざす彼の胸元に剣を突きさしたところで物語は終わった。
今月号は、その続きから始まる。「あぁ!!杜子春の運命や如何に!!」
—なんと—
絶命した杜子春の体から魂が抜け出して「地獄」の底へ降りて行ったのだ。
それは、ひゅうひゅうとさまよっていたが、森羅殿(しんらでん)という立派な額の掛かった御殿(ごてん)の前に降りると、もとの杜子春の姿となった。
そこにいた地獄の鬼どもは、その姿を見るやいなや周りを取り巻いて引き立てた。
御殿の階段の前へひれ伏せさせると、そこには、真っ黒な装束に金の冠をかぶり、いかめしくあたりを睥睨(へいげい)する一人の王様がいた。
これは、かねてうわさを聞いた「閻魔(エンマ)大王」にちがいない。杜子春はどうなることやらと恐るゝ身をかがめてしまった。
「これ!!その方は何のために峨眉山(がびさん)の上に座っていたぁー(怒)」
閻魔大王の声は雷の如く響き、もう杜子春はぎゅっと身を縮め、思わず答えようとした。
—しかし—
あの仙人との約束をとっさに思い出した。
それは、「けっして口をきくな。」との言葉だった。
そこで、身をかがませながら黙っていると、
エンマ大王は烈火の如く顔中の黒ひげを逆なでながら、「その方は、ここをどこだと思う。すみやかに返答せよ。さもなくば地獄の呵責(かしゃく)にあわせてくれるぞ!!(怒)」
—が、しかし—
杜子春は唇ひとつ動かそうとはしなかった。
それを見た大王は、すぐさま鬼どもに何かを言いつけると、彼らは一同にかしこまり、杜子春を引きずり回しては、それはゝ、この「さわやか説法」の紙面では書き表わせないほどの責め苦で、責め立てた。
それでも、杜子春は耐えに耐えて、ひと言も口をきかなかった。
さすがの鬼どもも、あきれはててその責め苦を止(や)めてしまったのである。
困りはて、エンマ大王のもと、森羅殿の前にまた杜子春を連れて行くと、
「大王様、この者は、もの言う気配がとんとありません」
と、口をそろえて言上(ごんじょう)した。
エンマ大王は眉をひそめて、しばらく思案にくれていたがハタッと何かを思いついた。
「そうじゃ。確か?こいつには?」
大王は、側にいた鬼になにやら耳打ちすると、鬼は大きく頷き、たちまち風に乗って、地獄の空に舞い上がっていった。
しばらくすると、その鬼が、2頭のけものを駆り立てながら森羅殿の前にカンラカンラ笑いながらやって来た。
それを見た瞬間、杜子春は驚いたの驚かないの!!心臓が口から飛び出るかのように驚いた。
—なんと—
それは2頭とも、姿はやせた馬だったが、顔は夢にも忘れられない「亡くなった父と母」ではないか。
「こりゃ!!その方は何のために峨眉山の上に座っていたのじゃぁー」
「早く言わんかぁー」「でなければ、その方の父母(ちちはは)に痛い思いをさせるぞー」
杜子春は、こう脅かされても返答しなかった。
エンマ大王は怒り狂ったかのように
「この不孝者めが。その方は自分の都合がよければよいと思っているのかぁー」
「打て!!鬼ども!!その2頭の馬をー」
ムチの音が響き、声にならない悲鳴が上がり、息もたえだえに2頭はドォッと倒れ伏した。
杜子春は必死になって、あの仙人の言葉を思い出しながら、かたく目をつぶっていた。
—すると—
その時、声とは言えないほどのかすかな声が聞こえた。
「しっしっ心配をおしでないよ。私たちはどうなっても、お前さえ幸せになれるのなら…」 「大王がなんとおっしゃっても言いたくないのなら黙ってていいんだよ!!」
それは、確かになつかしい母親の声だった。
杜子春は閉じていた眼を開けた。そこには息たえだえの母がおり、彼を見つめる優しい母の目(ま)なざしがあったのだ。
大金持になればお世辞を言い、一文無しになれば見向きもしない者たちとは違い「子を想う親」が、そこにはいたのであった。
杜子春は仙人の言葉を忘れ、そばに走りより、半死の馬の首を抱き、ひと声叫んだ。
「お母ぁ~さぁ~ん」と…。
フト、気づくと杜子春は、あの洛陽の西の門の下に夕陽を浴びていた。
「どうじゃな。俺の弟子になったとて、とても仙人にはなれはすまい。」
あの老人が呼びかけながら微笑んでいた。
「はい。なれません。なれませんでしたが、かえって嬉しい気がするのです」
「いくら仙人になれたとしても、私はムチを打たれている父母(ちちはは)をだまって見ているわけにはいかなかったのです」
「もし、お前がだまっていたなら…」と仙人は急に厳しい顔になり、
「俺は即座にお前の命を断ってしまおうと思っていたのだ」
「お前は、もう仙人になりたいという望みも持ってはいまい。大金持になることも愛想が尽きたはずじゃ」
「では、これから何になったらいいと思うな。」
「はい。何になっても人間らしく正直に生きていきたいと思ってます。」
杜子春は今までにない晴れ晴れとした心になっていた。
「そうか。その言葉を忘れるなよ。俺は今日限り二度とお前と会うことはないだろう」。
そう言って仙人はスタスタと歩き始めたのだが、急にまた足を止めて、こう言った。
「おぉ幸いに、俺は泰山(たいざん)という山のふもとに一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやろう。今ごろは、ちょうど桃の花が一面に咲いていよう」と、さも愉快そうにつけ加えた。 — 終り —
これが芥川龍之介の『杜子春』の物語である。
—ところが—
私は、このままでこの物語を完結させたくないのだ。
それは、杜子春に対してこう言いたいのだ。
「お前さんだけ泰山のふもとで幸せに暮らしていいのかい?」
「地獄にいた、お前の優しいお父さんとお母さんをそのままにしていいのか」と…。
「もし、そうなら、お前は大金持になって、三年で使いはたし、その時見向きもしなくなった人間達を薄情なヤツと言ったけど、実はお前さんが一番薄情な人間じゃないのか?」と言いたいのだ。
—実は—
「それからの杜子春」はどうなったのか。
それは次号にて…。
またまた、悪たれ川流之助が語ります。
合掌