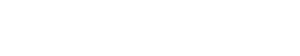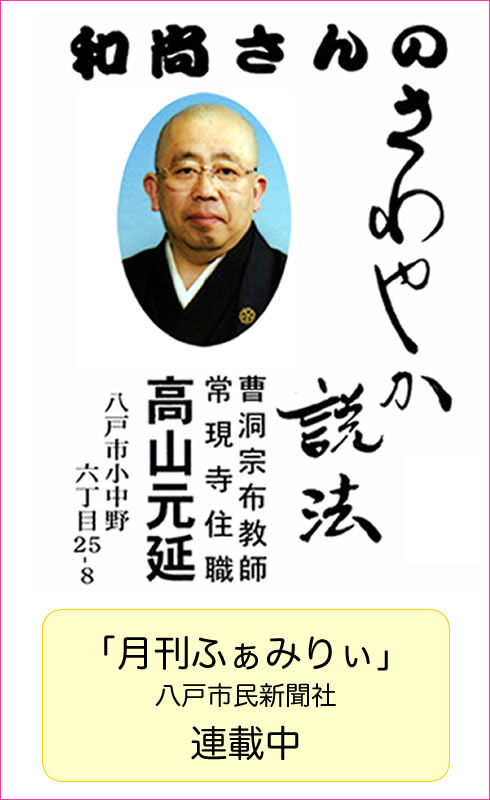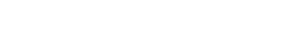和尚さんのさわやか説法264
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
先月号においては、毎日が「腹へったぁー」の仏教学専攻の貧乏苦学生が、いろいろなアルバイトをして、最後にたどり着いたバイト先は、
—なんと—
「お寺」のアルバイトだった。とのことを話した。
今回はその続き…。
こちらとは、大学で仏教を学び、禅を学んではいるが、檀家さんに対する実践面でいうと、それは、はなはだ心もと無い。
それでも、一応は「お経」は読めるし、着物や僧衣、お袈裟類は必需品として押し入れの奥には、しまってはある。
学生であるからにして、本山修行に行く前でもあり、僧侶としては半人前以下であるが、でも格好だけは一丁前である。
しかし、最も決定的な半人前以下であるのは、頭の「髪」の問題であった。
私は、学生時代は、親に内緒で髪を延ばしていた。
それ故に、大学の夏休みであろうが、冬休みであろうが、なかなか帰省することはなかった。
—何故ならば—
父親和尚は、帰ったとたん。
「なんだぁー(>_<) その髪はぁー」
「すぐ 床屋に行ってこい(>_<)」
と怒鳴られ、せっかく資生堂のMG5をつけながら丹誠込めて延ばした髪が、帰る度に丸坊主にさせられるからであった。
目標は、その当時、流行っていた「タイガーズ」や「テンプターズ」のグルプサウンズ型なのに。(涙)
—そんなわけで—
「お寺のアルバイト」は究極の選択肢であった。髪への未練…。
でも、やはり「背に腹はかえられぬ」というより、「腹」が「背中」にくっつく程の毎日を送っている私にとっては、お寺の「お盆のアルバイト」は、魅力的であった。
短期間(お盆の3日間)ではあるが、都内各地域のお檀家さんの家々を回っては、そこで「お盆のお経」を読み、一軒一軒からそれぞれ「お布施」を頂戴する。
その「お布施」の9割を、アルバイトである学生和尚に払うというのである。
—というならば—
髪への執着なんぞ、たいしたことではない。髪(かみ)は、そのうち生えてくるであろうから、「カミよりカネ」だ。
「神より仏」だ。との決心から、ともかく剃髪して、着物に僧衣を押入れから取り出し、東京は三ノ輪の曹洞宗は円通寺の門を叩いた。
—しかし—
世の中は、そう甘いものではない。働いてお金を得るということは、簡単なことではなかった。お寺のアルバイトとて、それは同じである。
都内の各地域に点在する、お檀家さんを捜し尋ねてお経を唱えることは、それはそれは大変なことであった。
朝早くから、夕方遅くまで、足を棒にして歩き回わなければならない。それに、それをきちんとやり遂げなければ、待っている檀家さんの期待を裏切ることにもなるだろうし、ましてや菩提寺たる円通寺様に迷惑を掛けることになる。責任は重大なのだ。
すると、次第に、単なるバイト賃欲しさのあさましい根性が、変化してきて、お盆の「棚経」での「経を読む」という意味の尊さが分かってきた。
—それと共に—
その円通寺での居心地の良さと、方丈様や奥様である「おふくろ」が、夕食の後に、いろいろなことを語り、バカな学生である私達に和尚としての本分を教えられていたことに気づかされたからである。
お盆の棚経回りに集まってきた学生は、皆なが「和尚の卵」である。将来は、それぞれの自分の寺に帰り、和尚の道を歩む者たちばかりだ。
—だからこそ—
その学生達を我が子のようにして育てていたのであろう。笑いの絶えない大家族的でありながらも、時には叱り、時には導き、温かく包み込んでくれた。
方丈様は住職ではあるが「稀有の人」である。工学博士の称号を持ち発明家でもあった。それも単なる発明家ではない。電気工学の大家であり、戦後間もないころの真空管の改良、あるいはTVのチューナー等には特許を所得していた。
故に、円通寺には寺専用の発明品があり、私ら学生達も、それを使った。
「自動墨すり器」なるものがあり、それは円形の硯(すずり)の上に、墨を固定させた機械で、スイッチを入れると「ウイーン」と音が鳴り、水を入れるだけで硯と墨が回転し「墨汁」が出来るのだ。
また、東京では年回法要の塔婆は地主だけではなく、参列者も「志主」となって何本も書く。それを同時に数本を書き上げるようにした「自動塔婆書き器」なんていう代物もあった。
あるいは、檀家名簿の「自動検索機」やら「自動○○器」なる発明品があった。
寺の庫裡の奥には、普通の寺にはない「工場(こうば)」があり、方丈様はいつもそこに立て篭っては機械に埋もれ、何かに没頭していた。
それでも夜、学生達が帰ってくると、工学の話やら、未来の電気社会の予測、電子社会の到来など、そして仏教学を熱く語るのである。
特に、多面体理論は熱かった。しかしこちらは何たって文系の学生だ。数式羅列でまくし立てられると、ただ口をアングリと開けるしかなかった。私にはチンプンカンプンだが、いつの間にか、多角的に人や物を見る方向性を学んでいた。
—それにもまして—
面白かったのは、奥様の存在だった。
先月号でも前述したが、奥様は、チャキチャキの江戸っ子娘であり、その「べらんめェ口調」で、私達学生を叱咤訓誡をする。
それが実に切れ味が良く、学生達が、くってかかっても、丁々発止と受け止めては、逆に言い負かし、まさにボケとツッコミの漫才化となるのであった。
皆なは「おふくろ」「おふくろ」と呼んでは、いつも笑いの中心にいた。
「おふくろ」の口癖は、「あんた達、学生和尚は 潰(つぶ)しが効(き)かないからなぁー」だった。
それは多分に、夫たる住職を常に見ているからであり、多才なる稀有たる「つぶし」の効く人の側にいるからであろう。
とある日、私はその口癖に反論した。
「和尚たるもの、潰しが効かない方がいいのだ。潰しが効くようじゃ、駄目なんだ。」
「それが和尚の本分を尽くすことじゃないのかぁー。」
「なぁー。おふくろ!!そうじゃないのか」とくって掛かった。
「てやんでぃ!べらぼうめェー。」江戸っ子弁の炸裂が始まった。
私も、それに負けじと、「俺はなぁー。八戸の江戸っ子でぇー。てゃんでぃ。」と訳も分からない口調で応戦した。
—そしたらである—
「ガッハッハッ」と大笑いした後、しみじみとつぶやいた。「こりゃ!!八戸の江戸っ子とやら」
「アタシゃね。アンタ達のことを思って言ってんだよ」
「潰しが効かなくなっていいんだよ。でもね、誰にも潰されないように、自分を磨けってことなんだよ」
「アンタ達が郷里のお寺に帰った時、潰しの効いた立派な和尚さんになってもらいたいからだよ」…。
私は完敗し、うなだれるしかなかった。
今思うと、あのおふくろの口癖は、きっとこういうことではなかったかと思う。
「何でもかんでも、他のことをやりなさいと言ってんじゃないんだよ」
「今の自分が、和尚の道の中でこそ、潰しが効くようにしなければならないということさ」……と。
この「潰しが効く」ということは、単に他の職業や仕事への適応ということだけではなくして、人間として、和尚としての適応力のことをいうのであった。
それは、宗教者として人々の心を救い、悩み苦しむ人々の心を救うには、檀家さんや社会の人々に尽くすには、如何なることにも潰しの効く力を磨いていなければならないという「自己錬磨」のあり方を言っていることに他ならなかった。
それから、私はあの円通寺には、お盆が終ってからも居候(いそうろう)よろしく、お寺の手伝いもしながら、腹の心配もなく、究極の「お寺のアルバイト生」となってしまっていた。
合掌