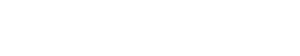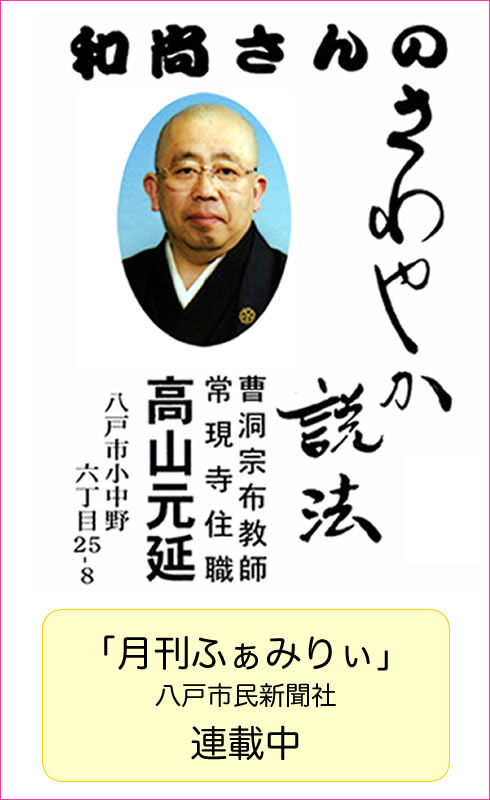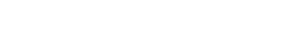和尚さんのさわやか説法216
曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延
母は我が子を救う為には、自分は「地獄」に墮してまでもと思うのだろう!!
八戸の偉人、近代の名僧と称讃される西有穆山禅師を「穆山」たらしめたのは、この「母の心」「なをの心」であった。
母なをは、おだやかな顔を「鬼」に変じて心を鬼にして
「何ば言ってるのだ!!万吉!!」
悪さを働いた幼児をたしなめ叱るが如く、いや我が子であればこそ、語気を強めた。
「したんども、おっ母さん!!オラだば八戸のお寺(でら)の住職さなれば、おっ母さんの側にいるごども出来るし…」
「湊衆の皆なも、お寺(でら)さん方も、そうせばいいっているんだよ」
「江戸で修行し、学問をしてきたオラの力をこの八戸で発揮すれば奥州一の和尚にもなれるって、皆なで誉めてくれるんだ」
—もう—
母は真底、我が子を救う為には突き放すべく覚悟をした。
「汝が幼き時、出家を志したその決心とは如何なるものや!!」
「八戸の寺の住職になる為のものであるのか!!皆なから誉めそやされて、その気になりおって(怒)」
「汝!!増長の慢心を起こしたのであろうが!!」
「いや!!そうではないっす。おっ母さん!!」
万吉こと金英和尚はタジタジとしながら、母の怒りを一身に受けるばかりであった。
「汝は、父や母を天に生ぜしめんと誓った、あの決心は如何なるのものであったのか」
「もし、汝がこの地に留まるというのであるならば、父も母もきっと天に生ずることはない!!」
—この時—
金英は、ハッと我に返った。
「そうだ!!私は、あの時、母様の菩提寺で地獄極楽の絵図を見た時おっ母さんは、私を育てる為には、地獄へ墮してもよいと言われた」
「だから、私は母様を地獄には行かせたくないと、心からそう思った。」
「あの時、私は誓ったではないか!!」
「一子出家すれば九族に天に通ずと…」。
金英の心には、幼き頃の情景が、そして、お坊さんになりたいと父母に懇願し拒む両親を説得した時の情景が走馬灯のように浮んできた。
—そして—
目の前にいる母が涙で、かすんで見えてきた。
「おっ母ぁさん!!」
声にならない声が金英の心の中で叫んでいた。
母は鬼の形相から転じて、優しく語り始めた。
「万吉!!今、お前がこの地に留まるならば、最初出家の志に背くのみならず、父母が汝を棄(す)てて出家させた志にも背くのである」
「いやしくも一旦、発心出家したからには、努めて智徳兼備の智識とならなければならぬはずである」
「母は、お前を近辺に置いて朝夕に汝を見るを楽しみと思わぬわけではないが……。」
「しかし、そうではならぬのじゃ!!」
そう言ったとたん、なをはスッと立ち上がって台所に向かった。
金英は、ただゝうなだれるばかりであった。母の情愛の深さを母の厳しき鉄槌を受けて、身震いがし、自分の心を戒めていた。
台所で母は、残っていた御飯で、ギュッギュッと音がするが如く「握り飯」をありったけ作りながら心の中で叫ぶ。
「万吉ぃー。万吉ぃー。」
「もう、この豆腐屋『うんど屋』の敷居は跨いではなんね!!」
「オラだって、お前ば側さ置いでおきたいよ お前と一緒にいれば何ぼ幸せだが!!何ぼ楽しいんだがぁー」
「だけど、それだば、わがねェんだ!!」
「オラの為でない。万吉の為にも、もう敷居は跨がせねェんだ!!」
なをは相反する二つの心の中で揺らぎ戦っていた。
—そう—
どちらも「母の心」であり、「母の愛」なのだ。
「このぶっつの握り飯があれば、しばらぐ間(ま)に合うな!!」
なをは作り終わると夫・長次郎の仏檀の前に座ると、
「これでいがすべ、お父っあん!!もう万吉と二度と会うごどもねェがもしれないが…」
「万吉だば、ちゃんとした修行しねば…。」
「ここさ居れば、わがなぐなってしまうじゃ」
「お父っあん!!許してけろ!!」
「お父っあん 分がってけろ!!」
なをは、亡き夫に語りかけていた。
—そして—
その仏檀のそばにあった金英和尚の旅支度の衣から手甲、脚絆から網代笠(あじろがさ)らを抱えて、土間の外に放り出した。
「なっなっ何するんだ おっ母さん!!」
「万吉!!こごば出て行け!!江戸に戻り修行を続けろ!!」
「いいか!!お父っあんも許してくれだ!!」
「お前は、こごさ、いればよくないって言ってくれだ。オラのことは、お父っあんだば、あの世でちゃんと見守ってくれるって、しゃべってくれだ」
「何も、オラのごとば心配するな!!」
「いや!!おっ母さん、待ってけろ!!」
「さっさと仕度して、早く出て行げ!!握り飯も、ずっぱと作っだすけ!!」
そう言うと、たじろぐ万吉を追い立てて、外に出し、入口の戸をピシャッと閉めたのであった。
「おっ母さぁ〜ん!!おっ母ぁさぁ〜ん!!」
万吉は必死で、その戸を叩くが、母は、その戸を堅く押し
「万吉やー 万吉やー」と忍びに忍ぶ声がもらしていた。
なんという母の力であろうか。
母が閉ざした、うんど屋の戸は、ビクとも動かなかった。
いや、万吉は動かすことができないのではない。動かせなかったのである。
母の心を想い、母の押し殺した声が戸口からもれ聞こえた時、万吉は、その戸口にたたずむしかなかった。
—そして—
万吉は意を決して、戸の向こうにいる母に語った。
「おっ母さん!!私が悪うございました。心からお詫び申し上げます。」
「この、いたらぬ修行未熟の万吉を、これほどまで案じて下さり、ありがとうございます」
「万吉は、この慢心を邪心を捨て、江戸に戻り、もう一度、幼き頃の初心に返り修行致します。」
「必ず、母様を極楽に行っていただけるよう修行致します…」
「母様、お別れでございます。どうぞお達者でいて下さいませ(涙)」
なをは、我が子の声が胸にジンジンと響いていた。その胸は、かきむしるかのように痛い。
—しかし—
それでも妙なる安堵感があった。
「これでいいんだ!!これでいいんだ!!」
何度も自分にいい聞かせながらも、涙が頬を濡らす。
万吉の姿は、湊橋を越え、もう姿は見えなかった。
でも、母には我が子が胸を張り、堂々と旅立って行く姿は心の中に見えていた。
「万吉やぁー万吉やぁー。…。」
空には満天の星が輝いていた。
合掌